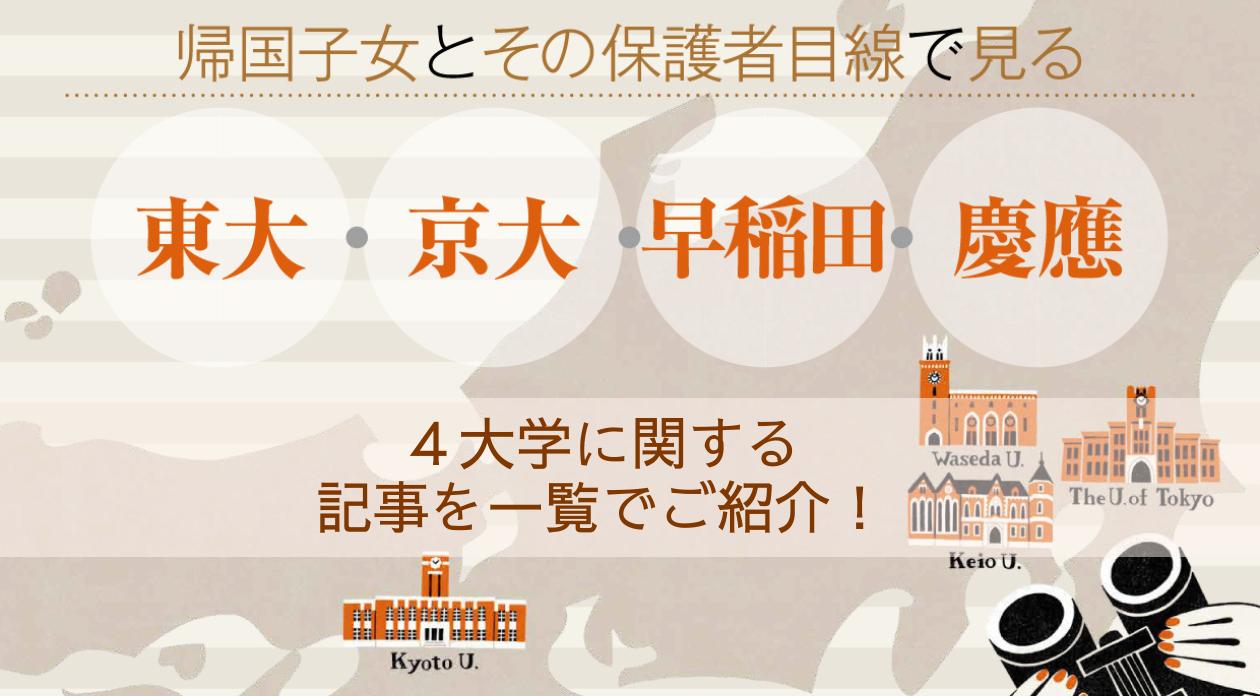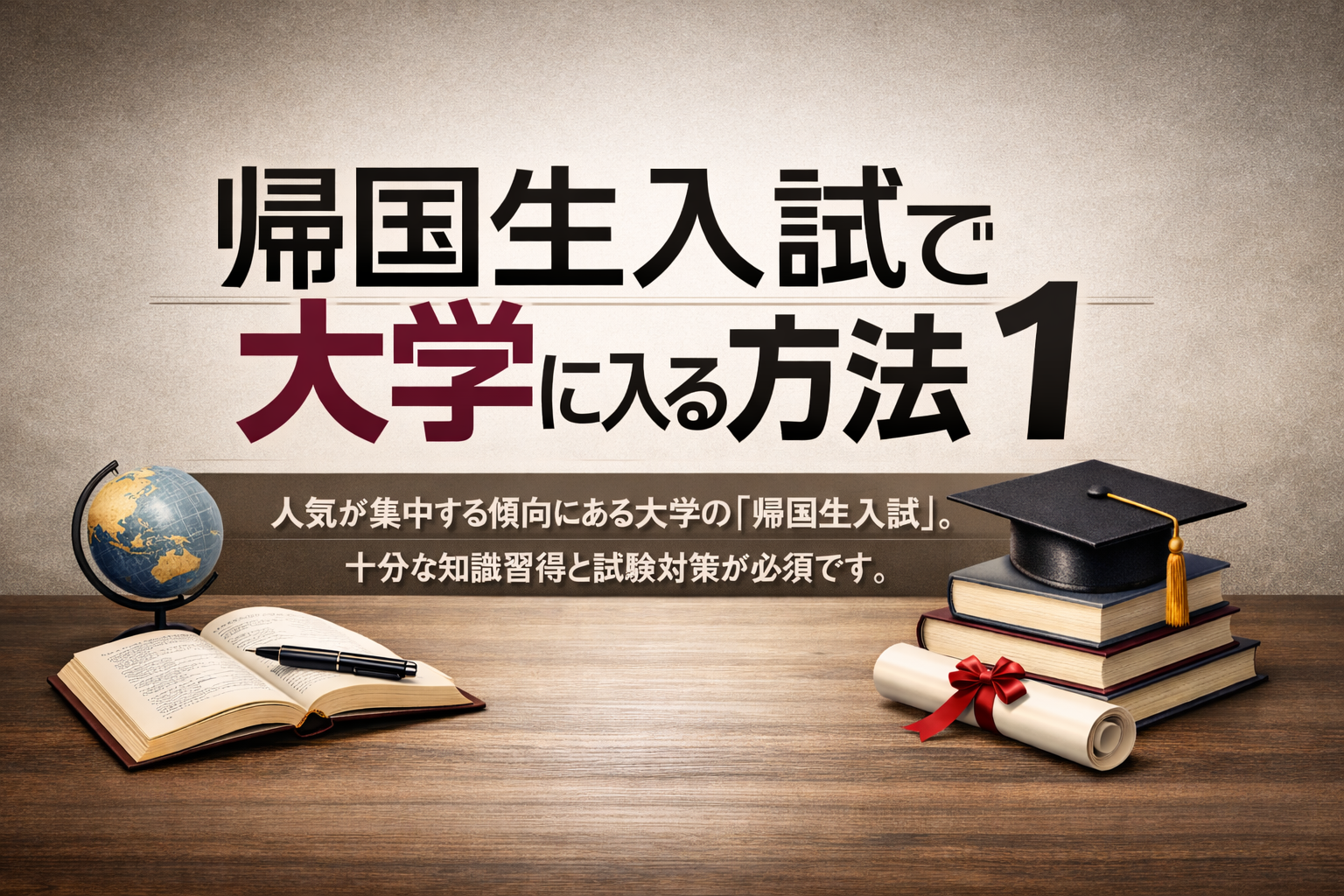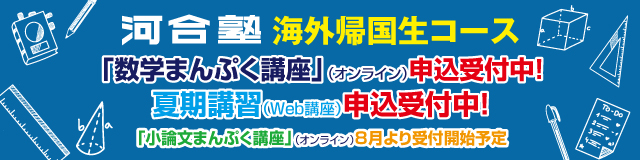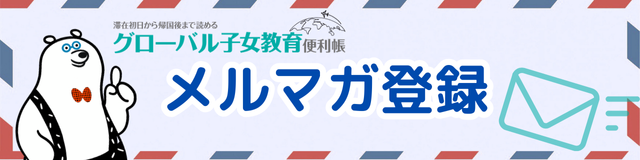STEAM教育とは? 内容やメリットを分かりやすく紹介!

皆さんは、「STEAM教育」について、見たり聞いたりしたことはありますか? 日本では、最近、さまざまな場所でSTEAM教育という文言にふれる機会が増えています。私立の中高一貫校での説明会や学校案内、プログラミングスクールのパンフレットに書いてあったり、知育教材のパッケージにも「STEAM教育対応」などという記載のシールがついていたります。「なんだかすごそうだけど詳しくは知らない」という方へ、STEAMの内容やメリットについてご紹介します。
目次
STEAMって何の略?
STEAMは「スティーム」と読み、次の5つの頭文字をとった言葉です。
以前は「A」を除いた理数系の4分野(Science、Technology、Engineering、Mathematics)の頭文字を組み合わせた「STEM(ステム)」とされていましたが、2020年頃からArts(人文社会・芸術・デザイン)が加わり、現在のSTEAMになっています。
STEAM教育での学び方
STEAM教育では、この5つの分野を重視し、授業の中でさまざまに組み合わせながら学んでいきます(教科と教科を組み合わせながら学ぶので、教科横断学習と言います)。一例を挙げると、こんな感じです。
「理科の実験」STEAMで学ぶとこうなる(一例)
STEAM教育の目的
STEAM教育の目的は、AIやIoT(住宅・建物、車、家電製品、電子機器などさまざまなモノをインターネットにつなぐ技術)などが急速に進む現代社会で、問題を発見し、解決する力を子どもたちに養ってもらうことです。
複雑に物事が絡み合う時代で問題を発見し、解決していくためには、今までのように「文系」「理系」といった単純な分け方をせず、5分野の教科の学びを集結させて、さまざまな情報を活用しながら挑む必要があるからです。
STEAM教育の始まりはアメリカ
STEAM教育の前身であるSTEM教育が誕生したのは、IT化やグローバル化に対応する人材育成の必要性が叫ばれつつあった2000年前後のアメリカです。その後、2009年に、STEM教育の質を上げるために、多額の民間投資が始まりました。そして、2013年に、当時のオバマ大統領が発した「新しいゲームを買うだけではなく、作ってみよう!最新のアプリをダウンロードするだけではなく、創造してみよう! スマホで遊ぶだけではなく、プログラミングしてみよう!」という言葉によって、全米に浸透しています。
ちなみにイギリスでは、2004年に「科学とイノベーションにつながる投資に関する10ヵ年計画」を打ち出しています。そしてEUでは、2015年に「EU STEM Coalition」というプラットフォームを創設し、産官学で連携してSTEAM教育を支援しようと動いています。
日本でのSTEAM教育
日本では、STEMとSTEAMの混在が見られるなどの混乱がありつつも、2018年の文部科学省発表の「Society 5.0に向けた人材育成 ~社会が変わる、学びが 変わる~」という人材育成方針でSTEAM教育が取り上げられるなどした結果、次第に広まっていきました。
そして今では、一部の先進的な私立学校だけだったSTEAM教育の実施が、公立校へも広がりつつあります。日本でのSTEAM教育の広がりについて、その一例をご紹介しましょう。
広がる日本でのSTEAM教育(一例)
●STEAMを取り入れた新しい学習指導要領がスタート
幼稚園では2019年、小学校では2020年、中学校では2021年、高校では2022年に、STEAMを取り入れた新しい学習指導要領が全面的にスタート。日本全国でSTEAMを取り入れた授業が行われています。
●「スーパーサイエンスハイスクール(SSH)」が200校以上に拡大
スーパーサイエンスハイスクール(SSH)とは、科学技術関係の人材を育成するための文部科学省の事業。先進的な理数教育を実施する学校を認定して、支援を行っています。この事業を開始した2002年の認定校は26校でしたが、25年近く経って230校以上に拡大しています。
●プログラミング教育の必修化・充実
小学校では2020年度からプログラミング教育が必修化。中学校では2021年度から「技術・家庭科」の技術分野でプログラミングに関する内容が充実。高校では2022年度から全員共通の必修科目「情報Ⅰ」と、選択科目の「情報Ⅱ」でプログラミングを学ぶことになりました。
●私立校で教科横断型授業が拡大
私立の中学校や高等学校では、「数学×物理」や、「化学×世界史」など教科横断型授業を行う学校が増加しています。また、「数学」や「物理」を英語を使って教える学校、STEAM教育を軸に学ぶコースのある学校も増加しています。こうした流れによって、世界最大の科学コンテストに参加したり、賞をとったりする日本人生徒も少しずつ増えてきていて、国際的にも一定の成果が出始めています。
●公立校でも教科横断型授業が増加
高校では、例えば「技術科」と「理科」を組み合わせてSTEAM教育を行うなど、公立校でも教科横断型授業を行う学校が徐々に増えています。また、ロボット教材を準備して、生徒にセンサー・モーターの制御をプログラムさせたりする先生も増えています。
STEAM教育は何かすごいの?
国際的な広がりを見せるSTEAM教育ですが、学ぶ側としては一体、何がすごいのでしょうか? その代表的な効果をご紹介します。
AIやIoTが進む未来を生きる子どもたちを育てるために、今後も拡大を続けるだろうSTEAM教育。拡大を続ける中で、『勉強は、受験攻略を目的にしたもの』ではなく、『勉強は、自分が創りたいものを創るためのもの』『勉強は、自分なりに答えを見出していくためのもの』というような、発想の転換が進むかもしれません。
STEAM教育のスゴさ5つ
親子でできるSTEAM教育とは?
理数系の知識や考え方を総動員させて問題を見つけ、解決できる力を身につけるSTEAM教育ですが、日常生活でも、その一部を実践できます。方法は、「問題点の発見と解決」を繰り返す声からをお子さんへすることです。ぜひ試してみてはいかがでしょうか。
STEAM教育につながる家での声かけ
●お子さんが小学生の場合…
小学生段階では、まずは理数的な領域に興味・関心を深めてもらうことが大切です。そこで、「物理現象に気づかせる声かけ」をしてみましょう。お子さんがいつも「あって当たり前」と感じているものに疑問を持てるような声かけがおすすめです。
【例】
コンビニで → 「冷蔵庫からペットボトル飲料を取り出したら、すぐに次のペットボトルが下りてくるのって便利だよね。どうしてそうなるのか、冷蔵庫の中を見てみよう」
公園で → 「落ち葉が木からゆらゆら落ちているね。不思議な落ち方だよね。葉っぱと同じように、薄くて軽い紙も不思議な落ち方をするかもしれないから、家で試してみよう」
●お子さんが中高生の場合…
中高生には、問題解決まで行きつく声かけをしましょう。コツは「日常生活の中から困った事情を探すこと」です。それを見つけたら、次の順に聞き、話をふくらませていきます。
1. どうして?
2. どうする?
3. 他に、この「どうする?」を活かしている場所やモノはないかな?
【例】
困った事例:瓶の飲み物のフタが手で開かない
1. どうして?…手で出せる力には限界がある
2. どうする?…テコの原理を活かした栓抜きを使えば、簡単に開けられる
3. 他に、この「どうする?」を活かしている場所やモノはないかな?…公園のシーソー、ハサミ