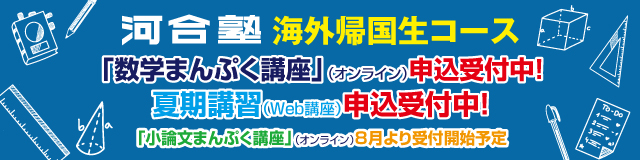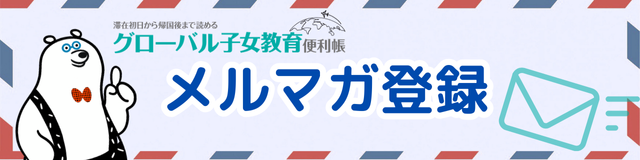【第5回】専門家に聞いた!後悔しない高校選びとは?

入寮したり、卒業後の進路を考え始めたり・・・。自立に向けた歩みの中では、様々な後悔も生まれてくるようです。教育ジャーナリストの中曽根陽子氏を含む専門家にお話を伺いました。
「帰国生受け入れ校に入ったが、実際に通う帰国生は少なく帰国生向けの英語の授業もない──」
【対応策】自分を発揮してみてと背中を押す
『もともと帰国生は多くの学校で少数ですから、帰国を“2第の異文化体験”と捉え、ここでも自分を発揮できるよう様々なことに挑戦してみよう』とお子さんに伝えるのも手。英語力に関しては、帰国生向けの外国語保持教室や英語塾、現地の友人とのオンラインでの交流、英語学習動画などの利用、活用を。英語能力試験の受験など階段式に達成できる目標を立てるとレベルアップしやすくなります(中山氏)。
【予防策】情報収集を2段階に分けて行う
高校在学中に帰国する可能性があるなら、情報収集をすぐにでもして学校の目星をつけておくのがいいという。「帰国から逆算して『この時期に帰国することになったらこの学校へ』といったシミュレーションをしておくのがおすすめです。加えて、編入試験の範囲・内容の確認と準備をしておくことも大切です。高校生ということで、学校探しはできるだけ本人が中心になって進め、保護者はサポート役にまわりましょう」(中曽根氏)。
「帰国が決まった時点で高2。あわてて受け入れ校探しをしたが、難航した──」
【対応策】地方の寮のある学校なども選択肢に
国公立は志望校の学区に居住するという条件がつく場合があり、その学校の欠員次第にもなるためハードルが高い。見つけやすいのは私立だが、高2の3学期以降に受け入れがぐっと減る。高2の3学期以降の編入を希望する場合は、少数の中から探すか、通年で帰国生を受け入れている学校を探すかして、問い合わせを。「あるいは、地方の寮のある学校や、学習支援体制の整っている通信制高校を視野に入れるのも一案です」(中曽根氏)。
【予防策】すぐにでも情報収集をして準備を進める
高校在学中に帰国する可能性があるなら、情報収集をすぐにでもして学校の目星をつけておくのがいいという。「帰国から逆算して『この時期に帰国することになったらこの学校へ』といったシミュレーションをしておくのがおすすめです。加えて、編入試験の範囲・内容の確認と準備をしておくことも大切です。高校生ということで、学校探しはできるだけ本人が中心になって進め、保護者はサポート役にまわりましょう」(中曽根氏)。
「『海外大学に行きたい』と言い始めたが、通っている学校に海外大学への進学実績がない──」
【対応策】留学斡旋組織にサポートを依頼する
「学校の先生に相談はできても、『エッセイの添削を何度もしてもらう』『書類の準備を手伝ってもらう』といった手厚いサポートをお願いするのは現実的ではないかもしれません。費用をかけて留学斡旋業者を利用するのがスムーズでしょう。合否には課外活動での成果も大きく関わります。活動は時間をかけて積み重ねていくものですから、海外大学への進学意志があるなら、動き出しは早ければ早いほどいいでしょう」(中山氏)。
【予防策】海外大学進学者は学校選びの段階で確認
「海外に滞在して楽しい経験を得た子どもが、機会があればまた海外に行きたいと思うのは自然なことです」と中山氏は話す。そのため、もし我が子が大学進学について深く考えていないようでも、日本の学校を選ぶ段階で、その学校の海外大学進学者数はチェックしておくのがいいという。「海外大学への進学に関する指導方法や内容については、学校に直接問い合わせて聞いてみるとよくわかるでしょう」(中山氏)。
「選んだ学校の寮の特徴とシステム、閉寮時期が親子共々合わなかった ──」
【対応策】愚痴や不満を共感的に聞くことから
「同期にも敬語を使う」「時間の縛りがきつい」といった独自ルールや慣習を入寮後に知るケースも。「疲れたお子さんを元気づけるのは親子の会話です。本人を労い、愚痴や不満を共感的に受け止めましょう。もしものときに頼りにしていい存在(本人の祖父母や親せきなど)を保護者が確保しておくことも大切です」(中里氏)。想定より閉寮が多いなどで対応しきれなくなった場合は、保護者の一方が本帰国するという選択も。
【予防策】閉寮時の居場所確保を第一に考える
「学校見学の際、寮の様子も見せてもらえるようお願いしましょう」(中里)。その際は雰囲気を確認しつつ、寮生に普段の生活について教えてもらうのがいいだろう。本人と保護者の困りごととしてよく挙げられるのは、閉寮時期や閉寮期間の長さ。まったく閉寮しないところもあるが、そうでない場合、閉寮時の居場所確保が重要課題に。また、子どもとの連絡手段や頻度に制限があるかも、事前に確認しておくのがいいという。
「ひとまず公立中へ編入し高校で意中の学校へと考えていたが、その高校が入試を廃止──」
【対応策】複数の学校を候補にして検討を
廃止が決定したなら、気持ちを切り替えて、ほかの学校に目を向けていくほかない。「その際、『ここはゆずれない』というポイントの優先順位を決めておくと、学校探しをしやすいと思います。探す際は1校だけにしぼるのではなく、複数の学校を視野に入れ、しっかりと募集要項の確認をしましょう」(中曽根氏)。帰国生入試と推薦入試の募集要項は例年6〜8月に公開されることが多い。時期を逃さずチェックしたい。
【予防策】募集要項は流動的なものと心得ておく
「私立の中高一貫校の場合は6年という枠組みで教育カリキュラムを展開するため、もともと途中で外部からの生徒を入れるのが難しかった」という理由に、少子化の影響も加わり、高校入試を廃止する学校が増加中。廃止までいかずとも定員を減らす中高一貫校や私立高校も増えている。「募集要項は流動的なものになったと心得て、気になる学校の情報収集をこまめにすることで、動向をつかんでおきましょう」(中曽根氏)。
「取材・文/本誌編集部・庭野真美 イラスト/いそのけい」
お話を伺った方

公益財団法人 海外子女教育振興財団 中山順一(なかやま じゅんいち)氏
国際基督教大学高等学校に創立2年目から勤務。担当教科は理科(化学)。教頭として帰国生入試の書類審査などにも数多く関わる。現在は上記財団にて、教育アドバイザーを務める。(掲載当時)

臨床心理士、公認心理師 中里文子(なかざと あやこ)氏
児童相談所等で親子関係の心理支援に携わる。現在は児童精神科クリニックを中心とした社団法人METKIDSでスーパーバイザーとして活動。企業内カウンセラーとして従業員支援も行う。

教育ジャーナリスト 中曽根 陽子(なかそね ようこ)氏
日本国内200校以上を取材。海外の教育視察も行い、紙媒体からWEB連載まで幅広く執筆。講演活動も精力的に行っている。新刊「中学受験 親子で勝ち取る最高の合格」(青春出版社)ほか、著書多数。