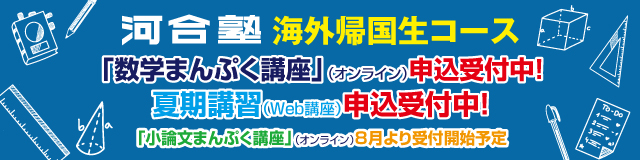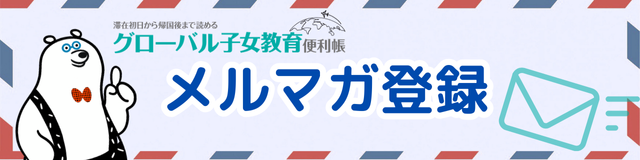【第4回】専門家に聞く!中学校選びの最新トレンドとは?
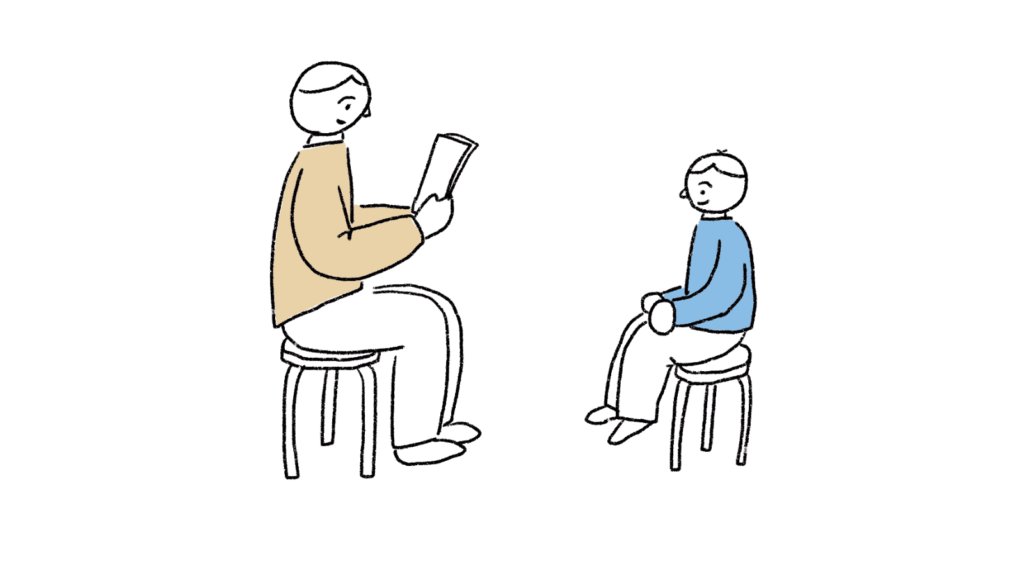
ハード面で効率が近づくもソフト面で国・私立の人気継続
「コロナ禍での休校時、私立の中学や高校は授業再開に向けて迅速に対応。タブレットやノートパソコンの配備やオンライン授業の開講など、その対応の速さや充実ぶりは公立を凌駕しました」(安浪氏)。2019年度から始まったGIGA(※1)スクール構想という国の施策により、公立の生徒にも端末が貸与され、ICT環境の整備もほとんどの学校で完了。ハード面でのアドバンテージはなくなりつつあるという。「それでも、首都圏でいうと2024年度の国立、私立を合わせた中学受験率は18.12%と過去最高の記録に。人気が衰える気配のない理由は、ソフト面にあると考えられます。まず、私立全般において、教育形態が非常に多様なこと。『特別な補習や授業を受け、得意なことを徹底的に伸ばす』『テストが一切ない』『中高で必ず海外研修がある』といったことが一例です。
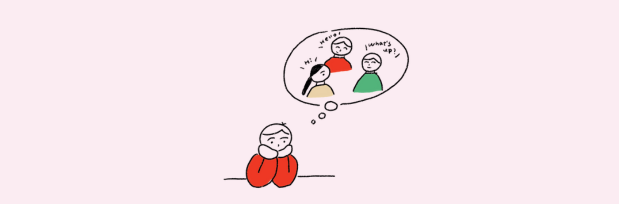
教育形態だけでなく校風も「大人しい男子が集まる男子校」があるなど多様です(安浪氏)。
そのように「教育形態や校風で我が子との相性を重視する」という近年の学校選びの傾向は、年々強くなっているという。実際、昨今は超難関校よりも中堅校(中学校偏差値45〜55のボリュームゾーン)の受験数の伸び率が大きくなっている。
公立中高一貫校の場合は、受験準備期間の短さや学費の安さ、さらに新学力(大学合格率)の高さも人気の理由の一つに。東京大学や京都大学といった難関国立大への合格実績が右肩上がりの学校も少なくないようだ。
安定志向の高まりで一般選抜以外の合格率重視も
昨今の中学校受験率がこうして高くなっている背景には、保護者の中に生まれている“子育てでの安定志向”があると安浪氏は推測している。
「少子化時代になり、一家庭ごとの子どもが少なくなったことで、『教育で失敗できない』『保険をかけておきたい』と考えるケース、あるいは教育費を集中的に注げるケースが増えてきているということでしょう」(安浪氏)。
また、中学校を選ぶ時点で大学進学をより明確に意識する家庭も増加中。大学附属校の人気は言うまでもなく、最近では「大学の合否を決定する際の総合型選抜(※2)や、学校推薦型選抜(※3)に強い中高一貫校を選ぼう」と考える保護者も増えてきているという。
「2021年以降、保護者世代の多くが経験した一般選抜での大学入学者は50%以下になりました。ですから、増加している総合型選抜や学校推薦型選抜での大学進学を中学選びの時点で意識するのは、理にかなっていることと言えるのでしょう。将来の予測を立て、早めに考えたり動いたりすることは、幸せな学校選びのコツとなります」(安浪氏)。
文部科学省の「国公私立大学入学者選抜実施状況」によると、2023年度での一般選抜は47.9%、総合型選抜は14.8%、学校推薦型選抜は35.9%。ただし、難関国立大学や難関私立大学は、一般選抜の占める割合がまだ高いこと、難関校といわれる高校では、一般選抜受験を主な目標にしたカリキュラムや進路指導が展開されているところも多く、進路指導は念頭に置く必要がありそうだ。
※1…Global and Innovation Gateway for ALL
※2…旧AO入試
※3…旧推薦入試
お話を伺った方

中学受験専門カウンセラー 安浪京子(やすなみ きょうこ)氏
算数教育家、株式会社アートオブエデュケーション代表取締役。大手進学塾にて算数講師を担当、プロ家庭教師歴20年以上。中学受験や算数に関する著書、連載、コラムなど多数。