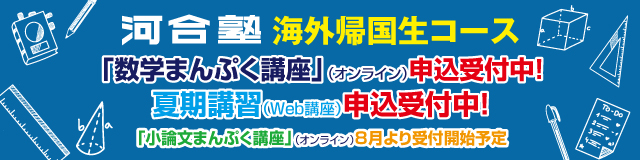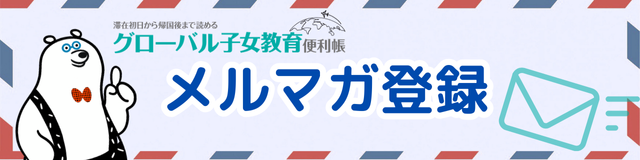【第6回】専門家に聞く!高校選びの最新トレンドとは?
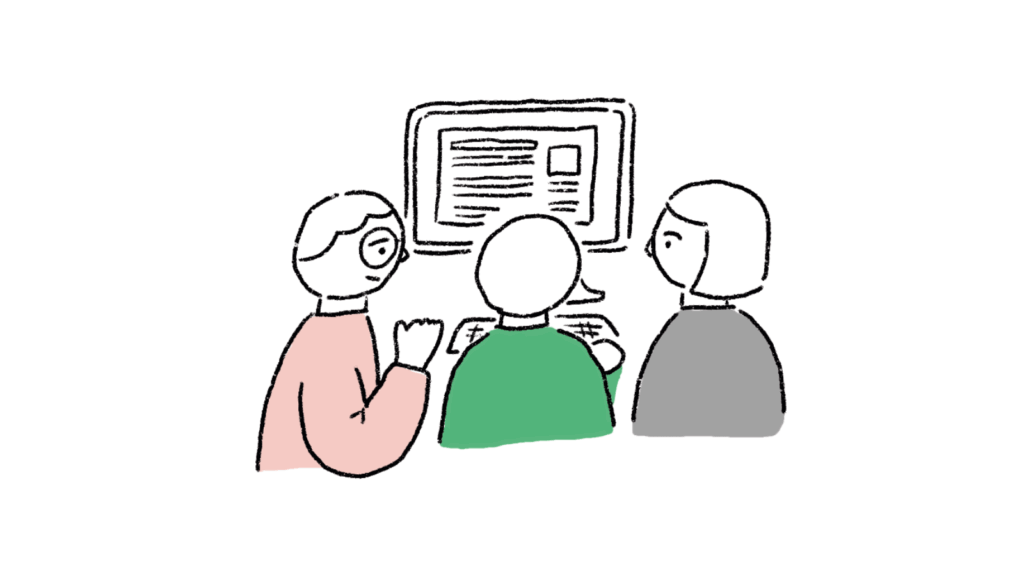
高大連携をうまく使える学校はこの先、伸びていく
近年のムーブメントとして挙げられるのは、高大連携教育の拡大。
「理由は二つあり、一つは大学側の事情です。少子化の影響で、定員未充足の大学が2024年度では全体の59.2%と過去最高になり、たとえ有名大学であっても安心できない状況となっています。そのため大学側は『高校とつながることで早めに優秀な生徒を確保したい』と考えているのです。もう一つは高校側の事情。新しい学習指導要領の施行によって、授業に地理探究や理数探究といった『探究』の科目が登場しており、その取り組みを大学と連携して行うことで他校との差別化を図れるのです。また、これまでのような『偏差値の高い大学に行けば人生成功』という価値観はすでに古く、いまは『大学に入学してからどれだけ自分に付加価値をつけられるか』を最重要視する時代。卒業までに大学に行く目的意識をいかに醸成できるかが高校の使命でもあると思うので、この意味でも、高大連携をうまく活用できる学校は伸びていくのではないでしょうか。幸せな学校選びをするために、こうしたこともぜひ頭に入れておいてください」(中曽根氏)。
さらに、高校受験者数の減少も、注目すべきトピックだという。
「18歳人口を1992年度と比較すると、2025年度には半数程度に。急激な少子化で高校受験者数も激減し、公立高校の統廃合は全国各地で起きています。少子化の影響はもちろん私立にも及んでいて、地方では特に定員未充足の学校が増加。優秀な生徒が高校進学時に別の学校に行ってしまわないようにという考えもあり、都心部では中高一貫校化を図る動きが進み、高校の募集を停止する学校が増加。高入生の定員を減らす学校も増えています」(中曽根氏)。

少子化などで統廃合が進むなか生き残りをかけ多様化の動きも
そうしたなかで、高校教育はどこを目指しているのか。キーワードとして中曽根氏は「探究」「グローバル教育」「デジタル・理数教育」の3つを挙げる。
「まず『探究』は、主体的な学びが求められる現代で欠かせないもの。大学の一般入試でも答えが一つではない問いに自分なりの答えを導き出す問題が増えていくので、生徒と先生の双方向型授業を行う学校が増加傾向に。また、留学制度を設ける学校、海外の高校卒業資格も取れるダブルディプロマプログラムを採用する学校も目立ってきており、『グローバル教育』への力の入れようがうかがえます。そして『デジタル・理数教育』への注目度は、昨今の教育のデジタル化の流れとともに高まっています。2024年度、文部科学省は、情報・数学などの教育を重視するカリキュラムを実施しながら、ICTを活用した文理横断的で探究的な学びを強化する学校を“DXハイスクール”として採択しました(公立746校、私立264校)。今後そうした学校が、どのような内容の教育を行っていくのかにも注目したいところです。一方で、テクノロジーとデザインと起業家精神を同時に学ぶ神山まるごと高専、実学・実践を大事にするFC今治高校里山校のようなユニークな学校もできており、教育の内容面での多様化が進んでいく可能性もあります」(中曽根氏)。
お話を伺った方

教育ジャーナリスト 中曽根 陽子(なかそね ようこ)氏
日本国内200校以上を取材。海外の教育視察も行い、紙媒体からWEB連載まで幅広く執筆。講演活動も精力的に行っている。新刊「中学受験 親子で勝ち取る最高の合格」(青春出版社)ほか、著書多数。