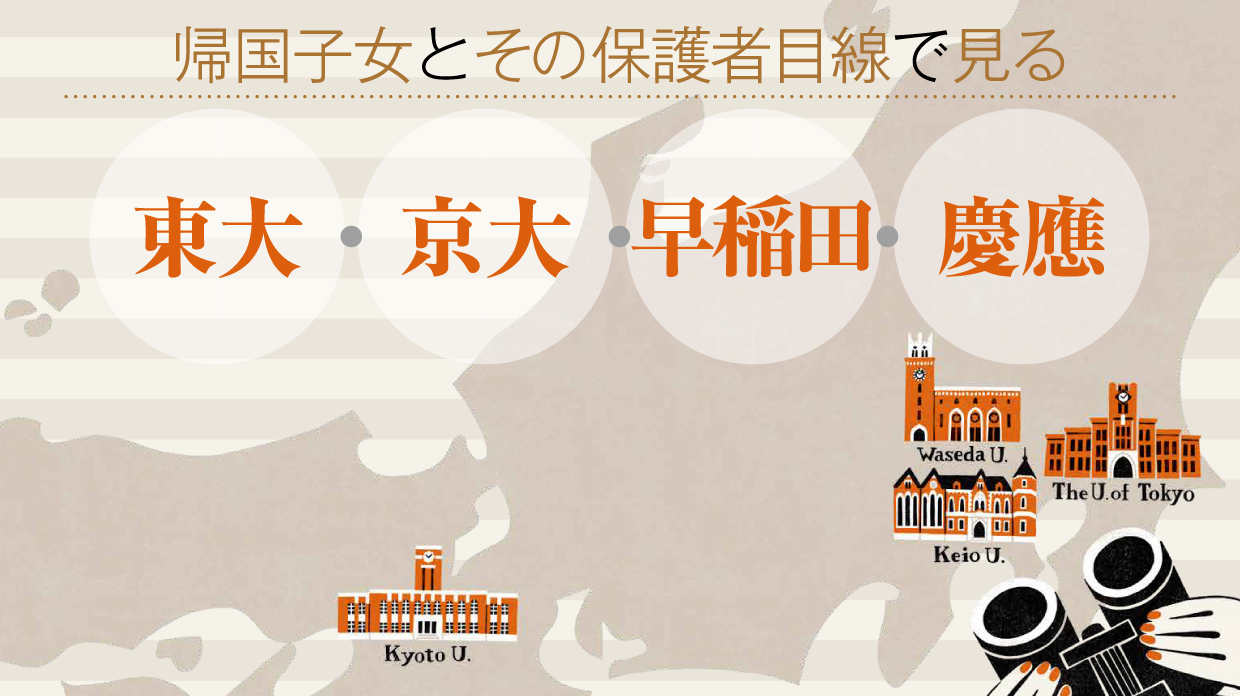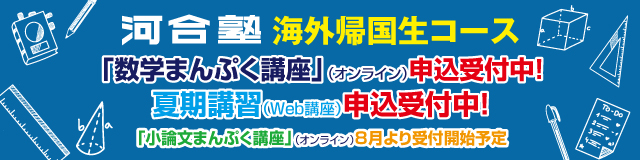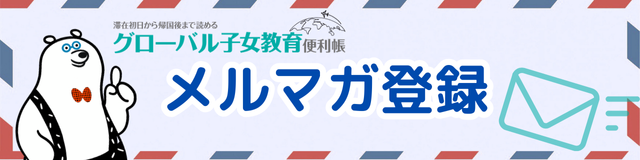【特集】帰国子女とその保護者目線で見る東大・京大・早稲田・慶應Vol.2~ランキングで知る4大学グローバル教育編~
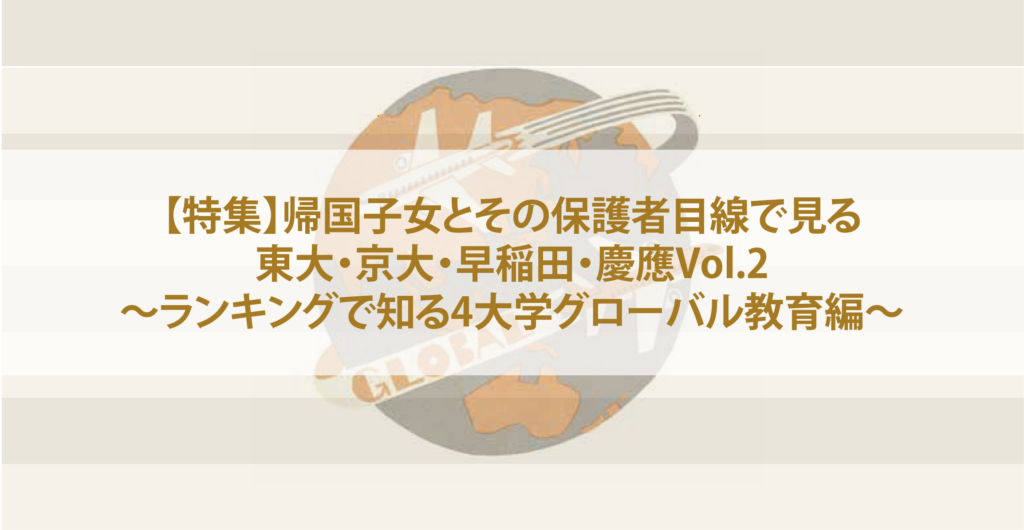
全12回でお送りする「帰国子女とその保護者目線で見る東大・京大・早稲田・慶応」
本特集において前回は教育ジャーナリストの中曽根陽子氏にお話を伺い、「学歴社会」から
「学習歴社会」へと移り変わる時代の中で、大学を“ブランド”ではなく“学びと成長の場”として捉えることの大切さを考えました。
【特集】帰国子女とその保護者目線で見る 東大・京大・早稲田・慶応
第1回:
4大学を知る、その前に…考えておきたい“学歴社会”のこと | グローバル子女教育便利帳
第2回では、様々なランキングを通して4大学をチェック。まずは留学など、気になるグローバル教育に関するランキングから。中曽根氏には、日本の大学と海外大学、それぞれが持つ強みなどについても伺いました。

世界大学ランキングが与える影響は大きい?
グローバル教育に関するランキングに着目すると、目立っているのは国際系の大学の取り組み。
「国際教養大学、立命館アジア太平洋大学、国際基督教大学、上智大学などがグローバル教育面で昨今の注目校だと思います」(中曽根氏)。
4大学は「日本人学生派遣数の多い大学」で上位にランクイン。留学先を国別に見ると、もっとも多いの がアメリカで15.2%、次いでオーストラリアで10.3%、韓国で9.4%、カナダで8.5%となっており、専攻分野別に見ると人文科学が約半数の50.2%、社会科学が9.7%、工学が9.4%となっている。
近年、大学を選択する段階で海外大学への進学を視野に入れ、実際に進学するケースも増加しているが、中曽根氏はその理由に次の3つを挙げている。

「第一に、大学の世界ランキングへの意識の高まり。欧米の大学が常に上位を占め、日本の大学はアジアにおいてもランキングが低いことが度々報道され、劣後して見えること。第二に、グローバルキャリアへの意識の高まり。国際機関や外資系企業など、『世界で挑戦したい』と考える学生は現地の大学に直接進学したほうが有利と考えるケースが増えていると思われること。第三に、海外大学の入試制度の柔軟性。例えばアメリカの大学入試では総合的な人物評価が行われ、日本の比較的画一的な受験制度に疑問を抱く生徒にとっては魅力的な仕組みになっていると思われます」(中曽根氏)。
帰国子女の場合は「海外の教育のよさや自身との相性のよさを知っている」という理由も考えられるだろう。もちろん、海外ではなく日本の大学に進学する優秀な学生も多い。
「そうした学生たちには、国内外の資源を効率的に活用して自律的に学びを構築できる能力が備わっています。また、帰国生なら特に日本社会に対する問題意識や変革意志もあるはず。そして長期的視野・戦略性を持って海外進出を検討している可能性も考えられます。日本の大学でベースとなる力を培い、大学の留学制度などを活用してターム留学をし、大学卒業後に大学院や職業経験を通じて世界へと飛び出すという選択肢を見据えるケースも多いのではないでしょうか」(中曽根氏)。
※1・・・Times Higher Education「THE 日本大学ランキング」内「2023年度に外国語で行われた科目数」 ※2・・・1と同じランキング内「2023年度の在籍外国人学生数/在籍学生数」 ※3・・・1・2と同じランキング内「2023年度の留学者数/在籍学生数」
お話を伺った方
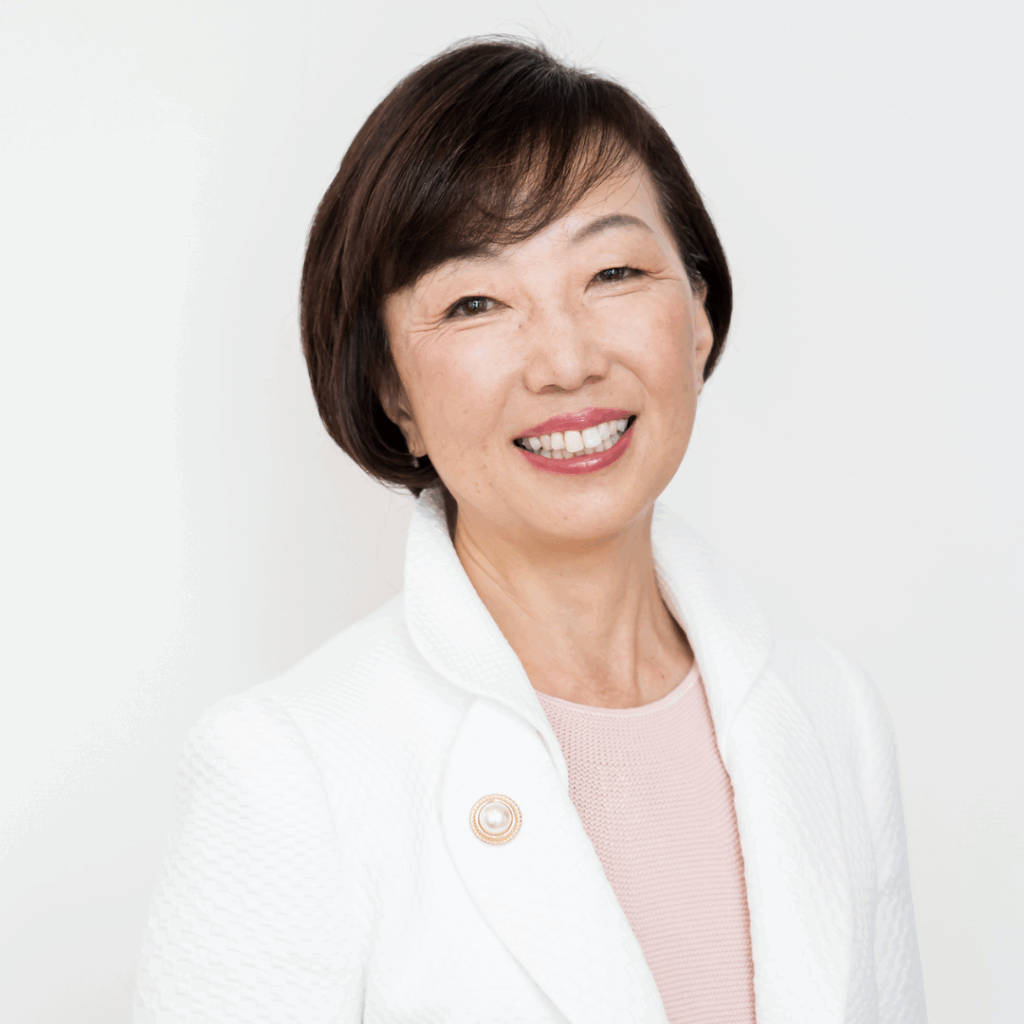
教育ジャーナリスト 中曽根 陽子
日本国内200校以上を取材。海外の教育視察も行い、紙媒体からWEB連載まで幅広く執筆。講演活動も精力的に行っている。『中学受験親子で勝ち取る最高の合格』(青春出版社)ほか、著書多数。