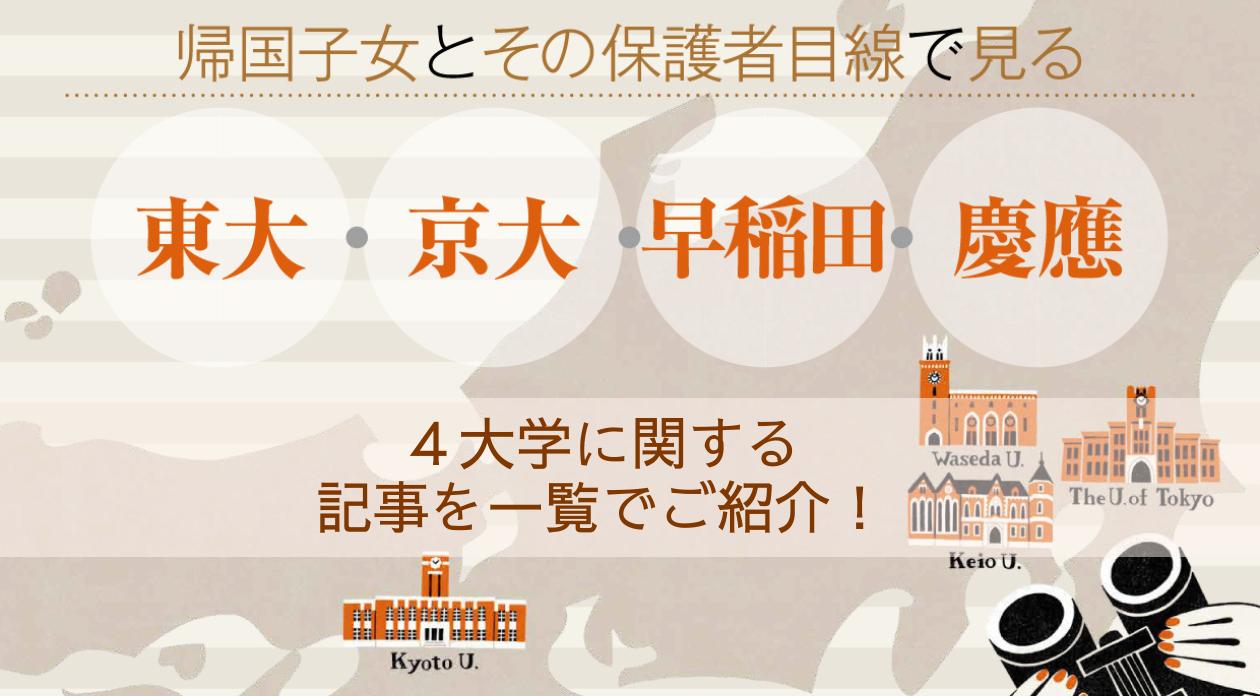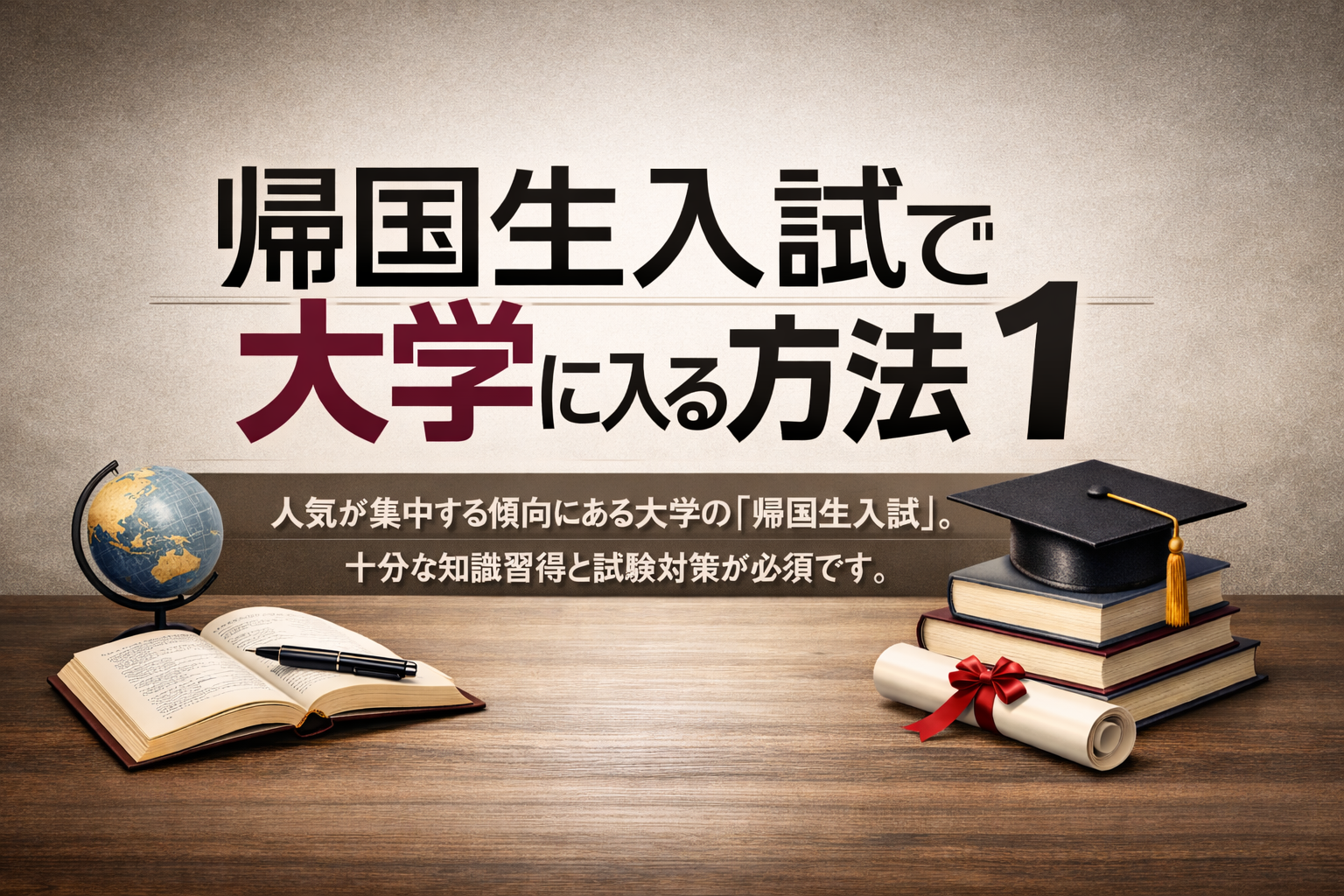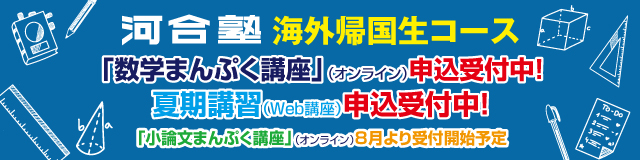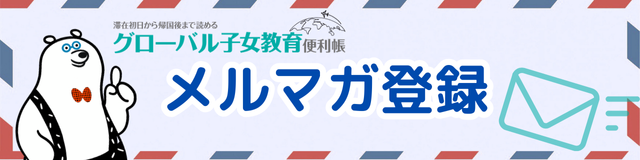3歳から中学生のプログラミングコンテスト、2,000作品超からグランプリ決定(後編)

豊かな発想力とプログラミング技術に感嘆
(前編)からの続き。
株式会社NTTドコモが主催するプログラミングコンテスト「第2回ドコモ未来ラボ」(以下、「ドコモ未来ラボ」)の最終審査会が3月22日(土)に開催された。3歳から中学生までの応募総数2,056 作品の中から事前審査を通過した16名が参加した。トップ写真は、グランプリを受賞した<未就学児童の部>の高鷹迅さん。
(後編)では<小学校4~6年生の部>と<中学生の部>の8名と、最終審査を終えた審査員の講評を紹介。また、本コンテストの意図などを主催者に聞いた。
<小学校4~6年生の部>
◆最優秀賞
根岸暖(ねぎし・だん)さん
作品名:「旅するフローティングハウス」
「海の上で自給自足できるフローティングハウスとワールドをRobloxで作成しました」という根岸さんは、昨年も最終審査会に出場しており、審査員の寛司久人氏(ひろし・ひさと:株式会社NTTドコモ ブランドコミュニケーション部長)は、「着実に進んでいる感じがして嬉しく思います」とチャレンジの継続と進歩を喜んだ。

◆発想力賞
お名前:森然(もり・ぜん)さん
作品名:「Learning to Hacking」
「サイバーセキュリティの基礎を誰でも気軽に学べるアプリ」をつくった森さんは、「ネットは悪意のある人が情報を盗んだり改ざんしていることを知り、サイバーセキュリティについて興味を持った」と述べた。

◆表現力賞
河地智陽(かわじ・ともはる)さん
作品名:「家族を超魅了!IoT調味料残量チェッカー」
「ソースや醤油などの調味料を置くためのBoxです。ただし、ただのBoxではありません。 作成した調味料残量チェッカーに調味料をセットすると、内部で調味料の残量(重量)をリアルタイムに計測し、調味料の残量が少なくなった状態が 12 時間連続で続いた場合、お母さんの携帯電話にメールを送信してくれます。これによって外出先からも自宅にある調味料の残量を把握でき、買い物時の買い忘れを防ぐことができます」

◆未来力賞
佐藤優成(さとう・ゆうせい)さん
作品名:「おにぎりファクトリー」
「鍋の中にお米を入れてタンクの中に水を入れると、自動でご飯を炊くことができます。ご飯が炊けたら、蓋を取ると、自動でふりかけをかけ、おにぎりを作ります」。お母さんに負担をかけずに自分で朝ごはんを用意したい、という動機から生まれたマシーンとのこと。

<中学生の部>
◆最優秀賞
若狭裕人(わかさ・ひろと)さん
作品名:「アルファベット列で作曲するアプリ」
「アルファベット列を音列に変換して、音として出力するアプリ。入力欄に入力されたアルファベット列を規則的に音列に変換します。また、アプリの使用者は音色や調などを選択することによって、作曲を楽しむことができます。音色や調を選択する際に音楽的な難しい用語が出てくるが、それらの用語を表示することもできます」

◆発想力賞
石澤滉基(いしざわ・こうき)さん
作品名:「ピンチを救え!!災害緊急お助けロボ」
「主に災害時、緊急時に使用する装置です。家の玄関に設置して使用します。 機能としては、遠隔で緊急事態であることを示したり(ラズパイ 3)、メッセージの録音(マイクロビット)、来客通知(ラズパイ4)、鍵忘れ通知機能(MESH)などがあります」

◆表現力賞
渡邊幸成(わたなべ・こうせい)さん
作品名:「戦って勝ち取ったカルピス(R)は世界一うまい」
「ボタンを押すとカルピスが注がれ、カルピスをかけて、足踏みで対決する二人用対戦型カルピスマシーン」。なお、小学生の頃からカルピスマシーンを作り続けていて、これが4代目にして初の対戦型だという。

◆未来力賞
柏春花(かしわ・はるか)さん
作品名:「空飛ぶ自動車とAI自動運転の未来」
「“空飛ぶ自動車”と“AI による自動運転”が普及した未来の交通システムを想像しました。地上と空中、それぞれの移動時間を比較し、空飛ぶ自動車によって移動時間がどれほど短縮されるのかをシミュレーションしました。さらに、地上で渋滞が発生する様子をシミュレーションし、空中では AI が自動車を制御することで渋滞が起こらない仕組みも再現しました。この作品を通して、未来の交通システムについて一緒に考えるきっかけになれば嬉しいです」

AI時代は「思いつき」が求められる時代
実際にプレゼンテーションを見たが、それぞれが身近な問題や好きなことに着想を得て、試行錯誤しながらオリジナルの作品を生み出していることが伝わってきた。すぐに役立ちそうな作品、ユニークな作品、夢のある作品など、子どもたちの豊かな発想力とプログラミングの技術に驚くばかりだ。
講評では、審査員の原田康徳氏が、AI時代を生きるうえで何が大切かを問う場面も。「これからAI の時代が来ますが、コンピューターが得意である必要はありません。求められているのは、『こういうことがやりたい』と思いつくことなのです。そういう思いのある人が、AIと一緒に色んなことをやっていけるだろうと思います。今日の皆さんはそういうことを思いついているし、やりたいと思ってるから、それをやめないでずっと続けていってもらえたら、みんなが大人になった頃に素晴らしい世の中になるんだなと、私ももうちょっと長生きしたいなと思いました」と、子どもたちにメッセージを伝えた。
子どもたちの未来を思い描く力を応援
本コンテストの企画・運営を担当している株式会社NTTドコモ ブランドコミュニケーション部の山崎由嗣(やまざき・よしつぐ)氏は、「弊社では2002年から子どもを対象とする創作絵画コンクールを開催していますが、裾野を広げるために、近年の教育現場で重視されているプログラミングのコンテストを始めることにいたしました。絵画もプログラミングも、子どもたちが未来を思い描く力を応援したい、という思いで実施しています。ですから、プログラミングの場合も、技術の優劣ではなく、アイディアが素晴らしければ受賞に値すると考えています」と話す。
そういった趣旨から、「ドコモ未来ラボ」のサイトでは、プログラミングの「始め方」を教えるページを用意するなど、プログラミング未経験者や初心者に向けたコンテンツづくりに力を入れているという。
「子どもたちのアイディアは十人十色で、大人が思いつかないような自由な発想に驚かされることも多いものです。プログラミングに興味をお持ちの親御さんは、ぜひドコモ未来ラボのサイトを見て学んでいただけると嬉しいです」と山崎氏は話す。
なお、次回(第3回)のコンテストも実施予定だ(現時点で詳細は未定。※応募は日本国内に在住の人に限る)。
(取材・文/中山恵子)