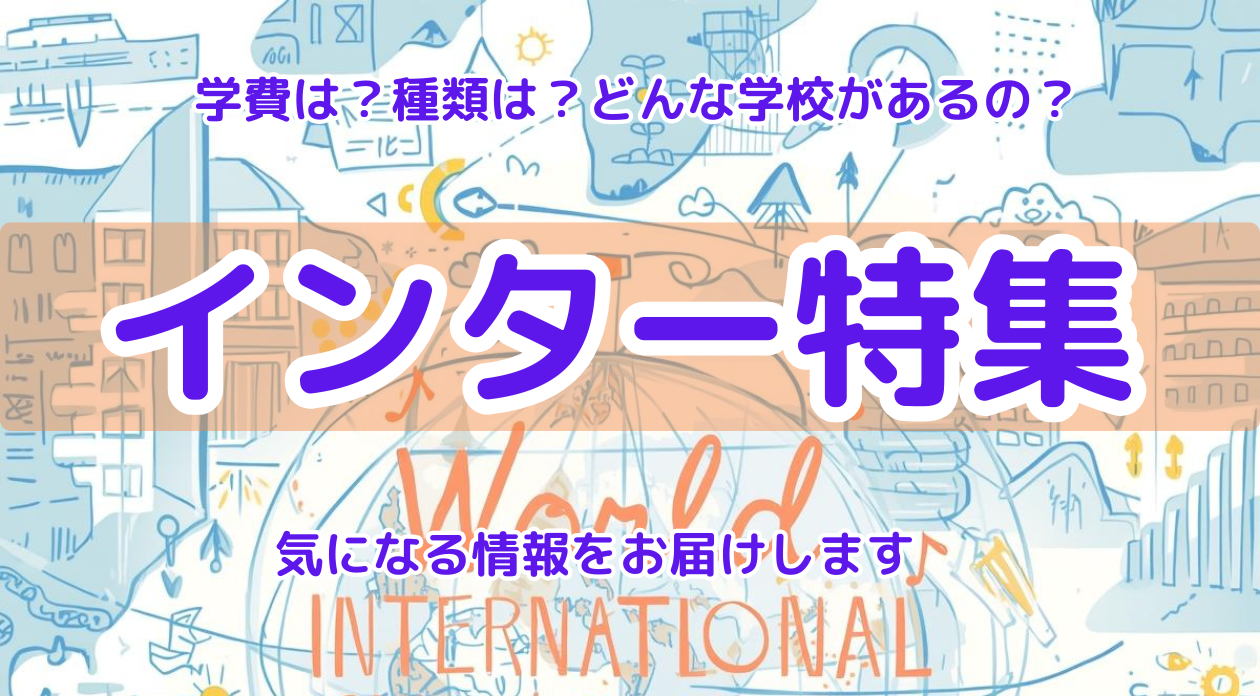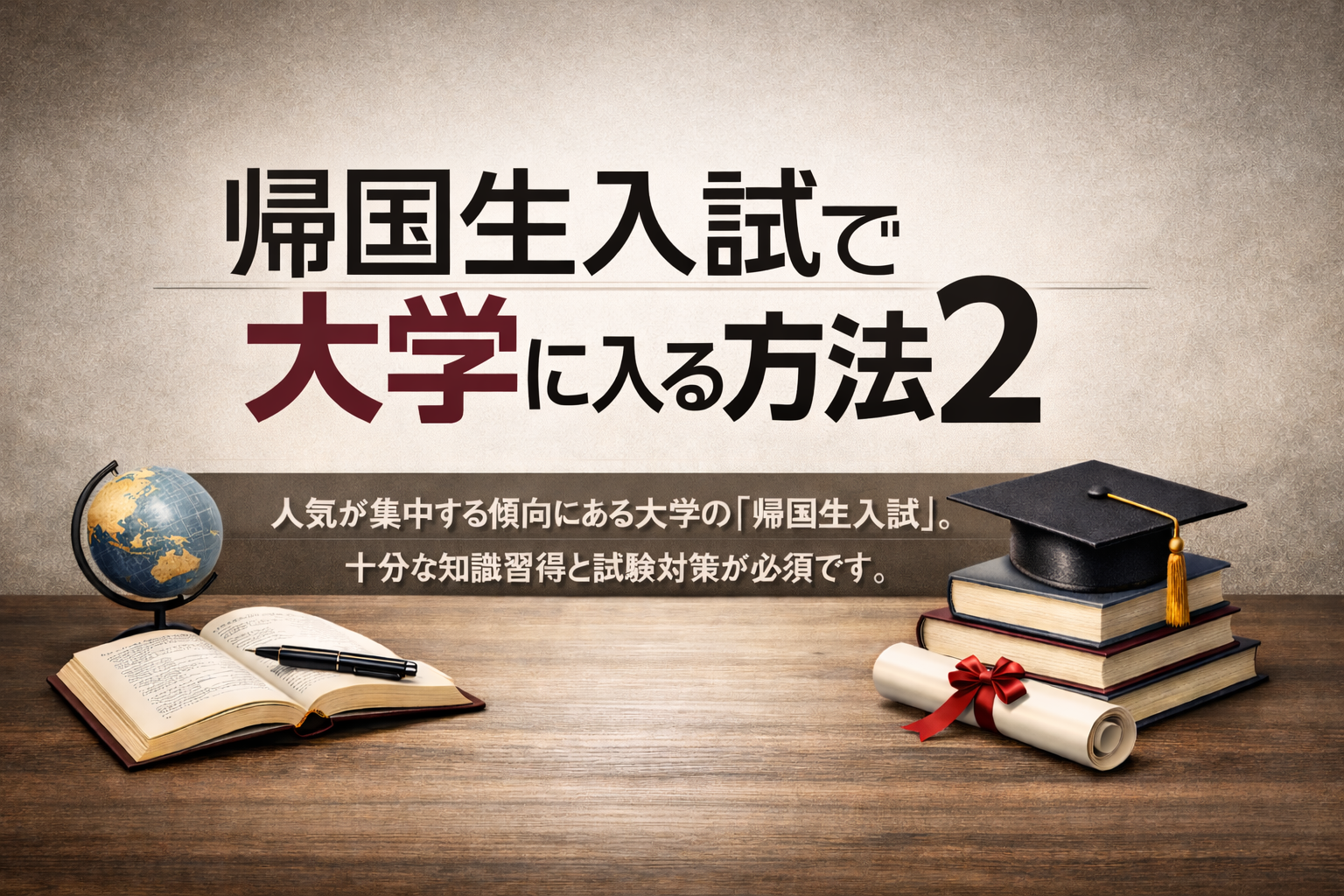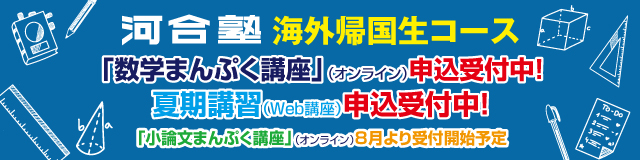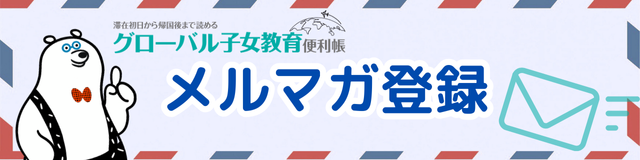渡航前とは大きく違う!?帰国前に知っておきたい日本の小中学校の学習環境|変化3
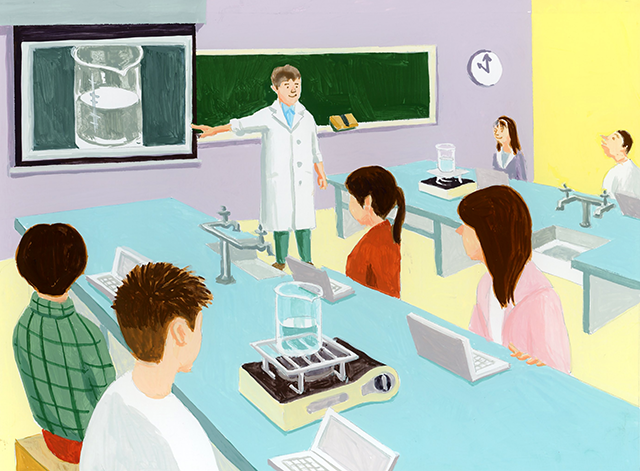
グローバル化、デジタル化、少子高齢化が進みゆくなかで、働き方改革もスタートして5年。様々な要因が絡み合い、義務教育は転換期を迎えています。今回は数ある変化のうち、「学習環境の変化」に着目。私立校だけでなく、公立校でも、時代に合わせた試行錯誤が始まっています。
変化3|不合理な校則の見直し
BEFORE
髪型、制服、かばんなどにこと細かな規制があった。生徒たちはただ黙って従うケースも多く、不満をため込んでいた。
AFTER
自分たちの人権や健康を害する恐れのある校則には黙って従わず、声をあげる生徒が出てきた。それで実際に、校則が変わった学校も。
変化は少しずつでも見直しは続いていく
髪が黒色以外・直毛以外であれば地毛証明を提出、冬は寒くてもマフラーの着用禁止、夏は半袖以外着用禁止、下着の色は白のみ…。
生徒の人権や健康を害する恐れのあるこうした校則が「ブラック校則」として認知され、社会で問題視されるようになったのは2017年から2019年頃にかけて。きっかけの一つは、地毛の茶色っぽい髪を黒く染めるように指導されて不登校になった大阪府の女子生徒を巡る裁判だった(※)。2021年には文部科学省が全国の教育委員会へ校則を見直すよう通達。翌2022年には、生徒指導の基本的な考え方をまとめた「生徒指導提要」を文部科学省が12年ぶりに改訂。社会の変化や教育的意義をふまえて絶えず校則の見直しを行うことなどが記載された。
「こうした変化を喜びつつも、念頭に置いておきたいことがあります」と話すのは、校則問題を研究する名古屋教育大学大学院教授の内田良氏。「それは“どんなに不合理な校則だとしても、見直しはスピード感を持って進むものではない”ということです。多くのケースにおいて生徒会が約半年から1年をかけて見直しを進めますが、見直し幅は“規定の靴下の色が一色だけ増えた”というように小さいことが多いのです。それでも、報道されないレベルで日本各地の学校で校則は少しずつ是正・刷新されています。今後もその傾向が続いていくでしょう」(内田氏)。
校則の見直しの一番のメリットは、生徒の人権や健康が守られること。「生徒自らが自分たちの生活ルールを考えることにも大きな意味があります。“社会の主権者”のマインドが育まれていくからです」(内田氏)。
変化の例|「生徒たちは校則の見直しから“自ら考えることの大切さ”を学んでいます」/国立市立国立第三中学校(東京都)
「毎日を快適に」という思いが原動力に
校則の見直しHistory
2022~2023年
生徒会が学校に掛け合って、私服で通学するカジュアルウィークを2度実施。校内に「校則を見直そう」という機運が生まれる。
2023年・6月
「校則検討委員会」を発足させ、全校生徒の要望を集約するところから校則の見直しを開始。
2023年・10月
見直した校則が学校側に認められ、施行に至る。
同校では生徒会のメンバーを中心に生徒自らが「校則検討委員会」を立ち上げ、主体的に校則の見直しを進めている。きっかけは2022年9月、暑さ対策の一環で、生徒会が学校に掛け合って私服通学をOKとする5日間の「カジュアルウィーク」を設けたことだった。翌年1月には期間を8日間に増やし、防寒を目的とした「冬のカジュアルウィーク」も決行。
「そんな流れから“毎日快適に、自分らしいスタイルで学校生活を送ろう”という機運が生まれました」(同校)。
この後、前述の「校則検討委員会」が誕生。同委員会を中心に2023年6月から約4カ月かけ、全校生徒の要望を集約し、精選・検討して学校側に提案する、というフローで校則を見直した。「集約と精選・検討には一人一台配備されているタブレットの表計算ソフトが活用されました。生徒たちは様々なことを考え、判断したため、見直した校則が施行された頃には“大仕事をやり遂げた”と感じた様子。今後も校則の意義を考えながら見直しを継続していってもらえたらと思います」(同校)。
子どもたちの反応
- 個人の判断で衣替え可能に。その日の気温に合わせた服装で登校できるようになり快適。
- 整髪料の使用OK、ヘアゴムの色なども自由。自分らしさを表現できるようになった!
※…2021年、大阪地方裁判所にて「髪の染色や脱色を禁止した校則は学校の裁量の範囲内で、頭髪指導も違法とは言えない」とする判決が示された。この判決結果に世論が納得せず、全国の校則の是正を求める社会的な動きが活発化。
あわせてチェック! 小学校では脱ランドセルの動き
「学校が指定する場合を除けば何を使っても構わない」という原則が周知されつつある昨今。2023年には通学用リュックを無償配布した自治体も。こうした流れから今後はランドセル以外の選択肢も当たり前になっていく可能性がある。
お話を伺った方

名古屋大学大学院 教育発達科学研究科教授
内田 良(うちだ・りょう)氏
専門は教育社会学。『だれが校則を決めるのか』(編書、岩波書店)、『ブラック校則』(共著、東洋館出版社)など、校則や学校リスクに関する著書や共著、編書多数。
取材・文/本誌編集部・庭野真実 イラスト/太田マリコ
※今特集に掲載している情報は、2024年2月現在のものです。国の教育方針等は変更される場合もあります。
【関連記事】