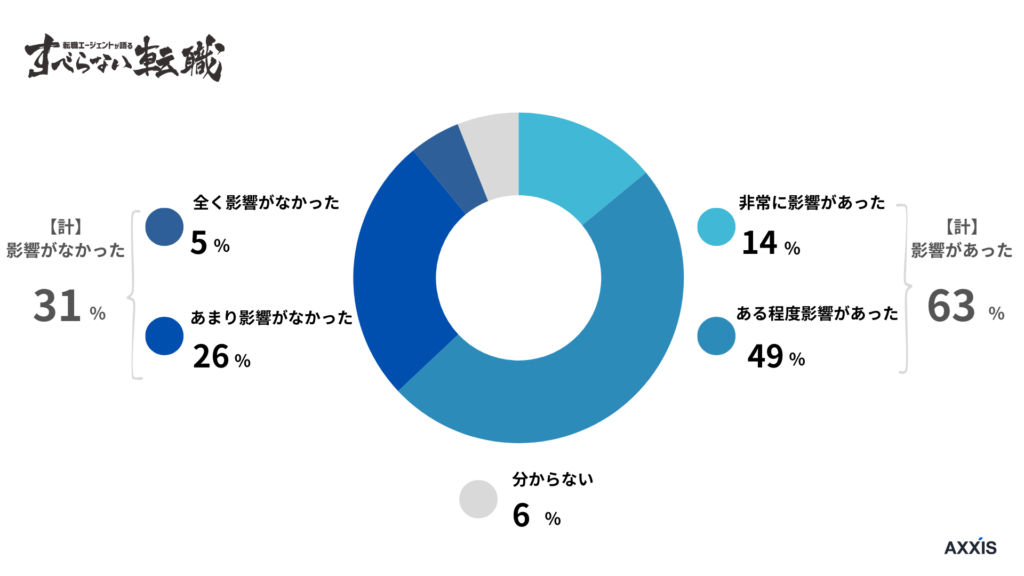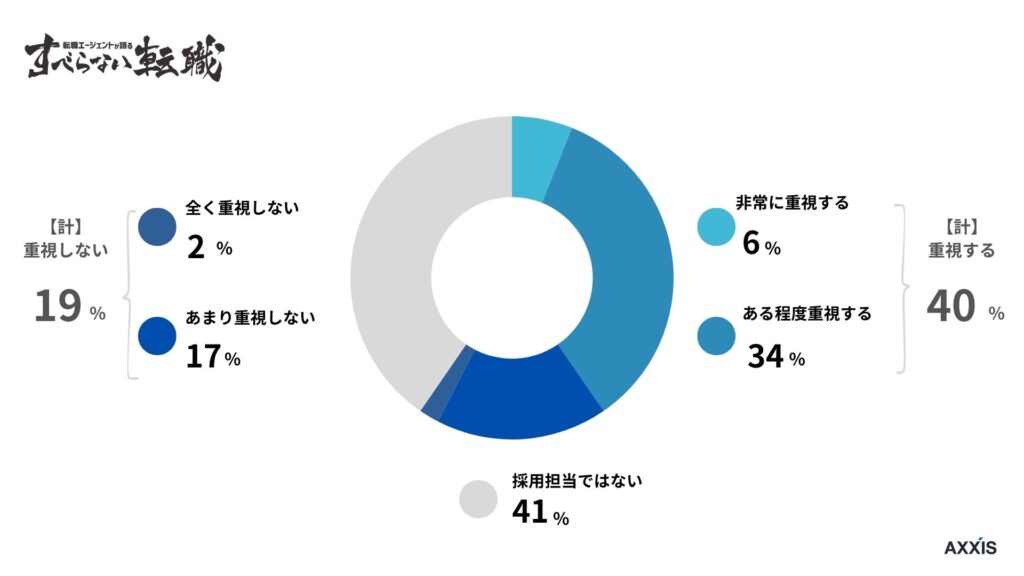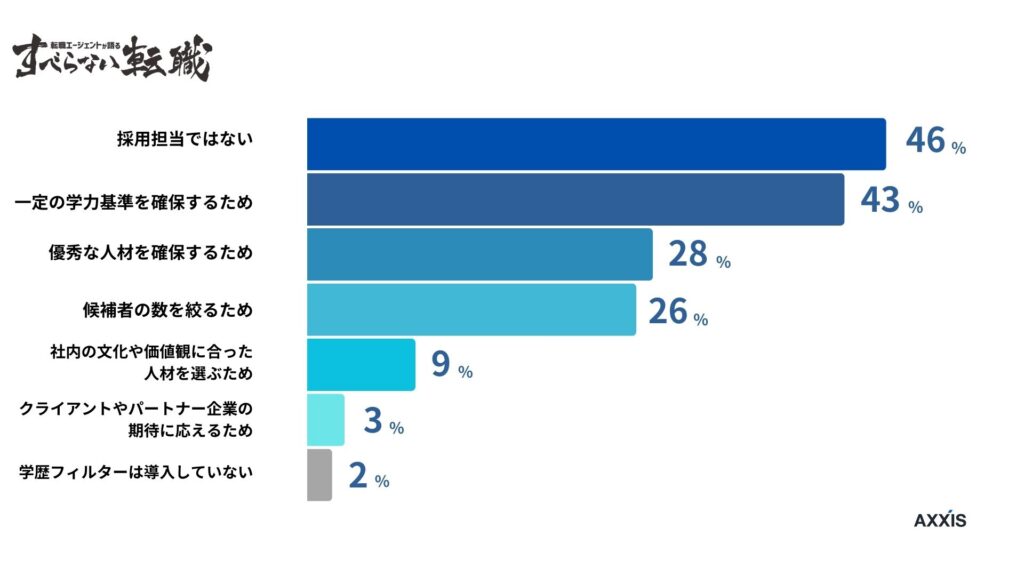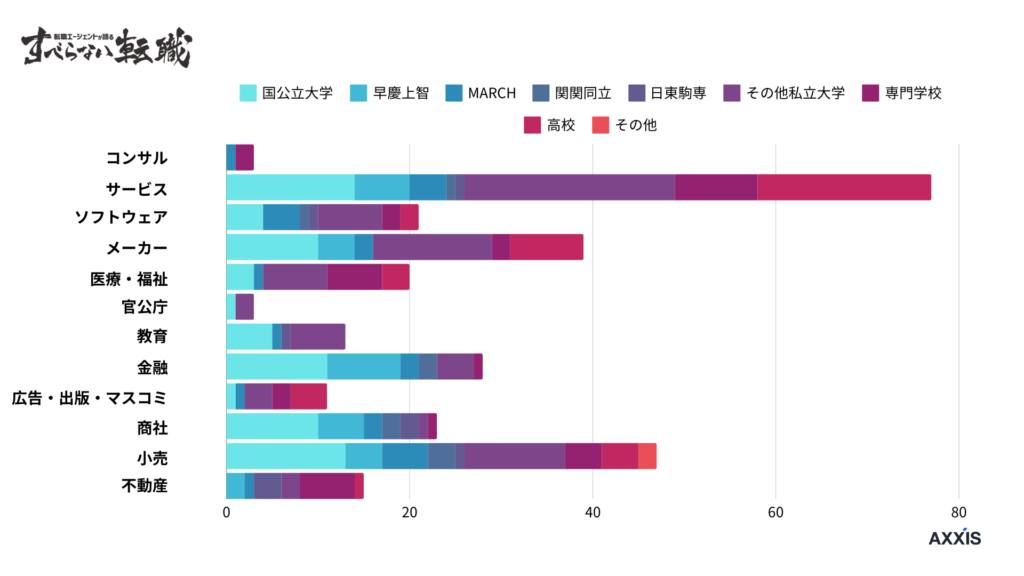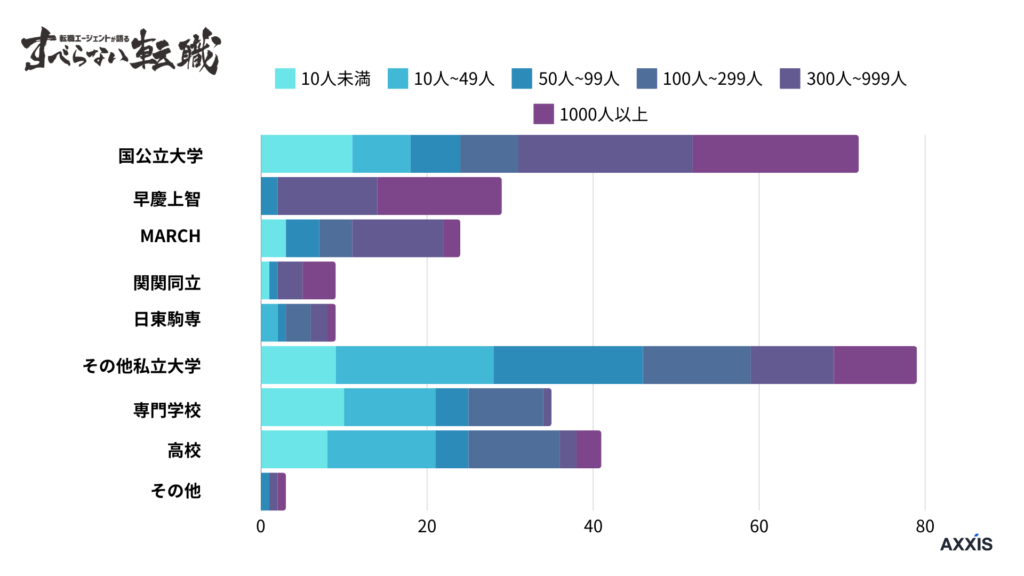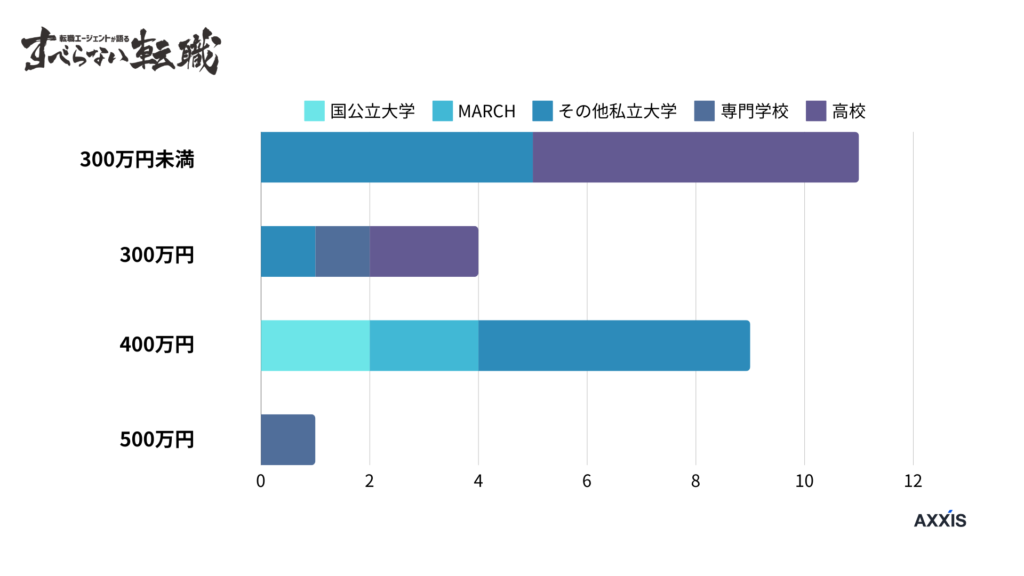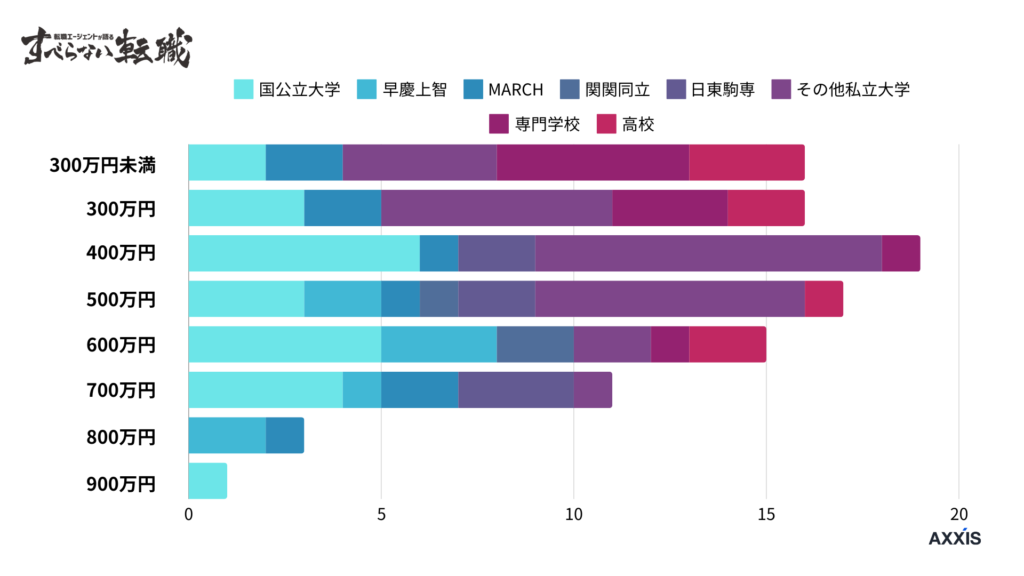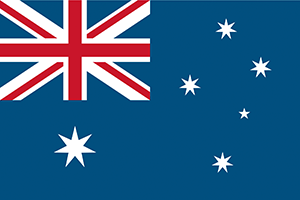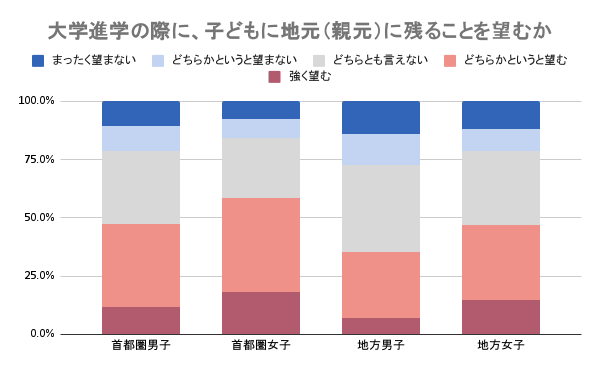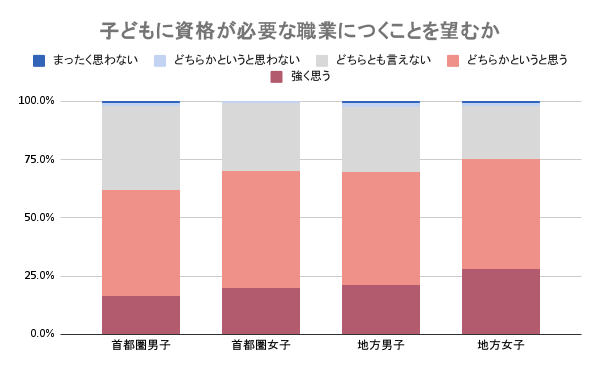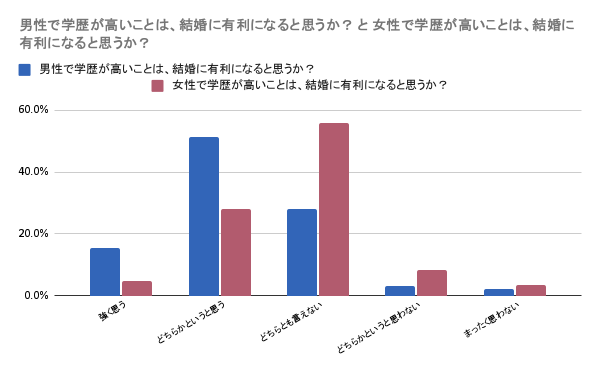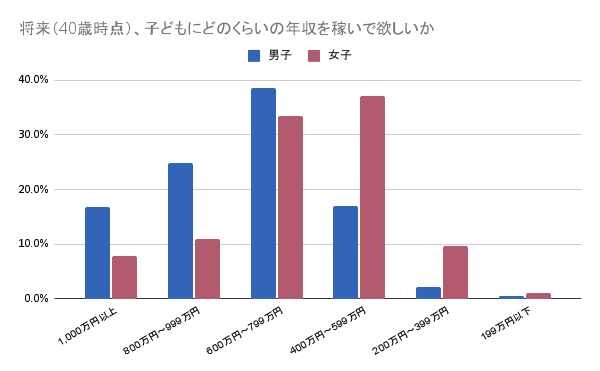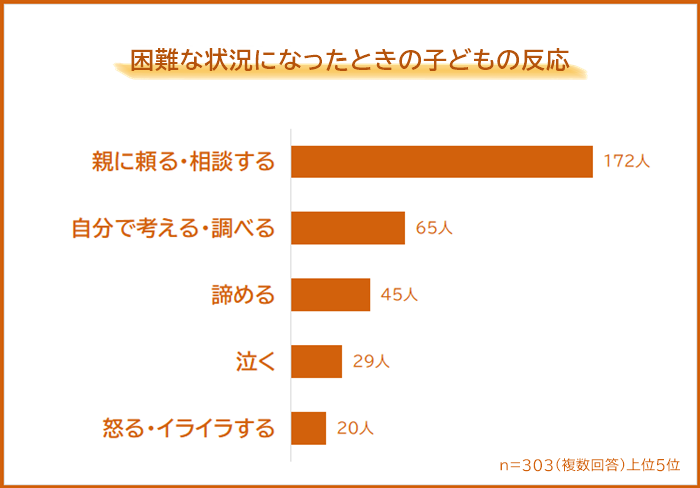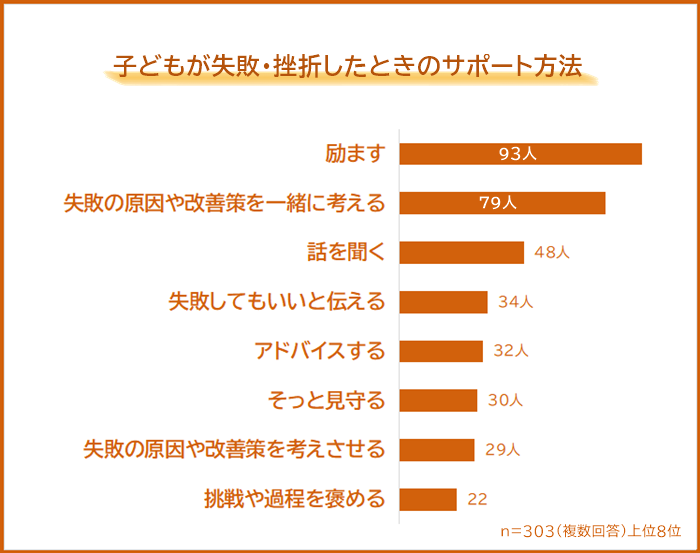マヨネーズを活用した食育活動で子どもたちを笑顔に(後編)
出前授業で食の楽しさを伝える
(前編)からの続き。
さまざまな食育活動を展開しているキユーピー株式会社(以下、キユーピー)。その取り組みの一部を紹介しよう。※トップ画像は「マヨネーズ教室」の様子。
前編で紹介した「ピーマンチャレンジ!」は幼児向けのイベントだが、小学生向けの食育活動としては2種類の出前授業を開催している。
「マヨネーズ教室」は、社内認定講師「マヨスター」(※マヨネーズや衛生、科学などの知識を伝え、マヨネーズ教室の運営を行うことができる資格。キユーピーの社内認定制度の呼称)が小学校を訪問し、食の楽しさと大切さを伝える活動だ。2002年より開始し、2024年度は全国99校の小学校で開催した。マヨネーズが何からできているのかをクイズで質問したり、実際に作って野菜につけて食べたり、といった授業を行うなかで、子どもたちに食べることの楽しさや大切さを感じてほしいという。
「SDGs教室」は、SDGsの17の目標のうち「目標12:つくる責任 つかう責任」を取り上げ、キユーピーグループのサステナブルな取り組みを交えて環境問題について自分たちができることを考えてもらうといった内容。調べ学習のみになりやすいSDGsの学習を、直接企業の担当者に聞くことができる点が好評を博しており、昨年度は全国70校の小学校で実施した。
海外では現地の味と混ぜて楽しんでほしい
キユーピーのマヨネーズは、海外でも販売している。海外製造の赤い網目のパッケージのものは日本と同じ「卵黄タイプ」にこだわった商品で、現地の食文化に合わせて工夫をしたひと味違うマヨネーズもある。また、海外の日本人学校からのオンラインでのマヨネーズ教室やSDGs教室の申込みも受け付けているという。
キユーピー株式会社 広報・グループコミュニケーション室 社会・食育チーム 羽生田雅子(はにゅうだ・まさこ)氏は、海外在住者に向けて、「各国で多種多様な調味料が手に入りますが、『マヨネーズはやっぱりキユーピー マヨネーズ』というお声をいただくたび、私たちはとても嬉しく、励まされています。マヨネーズはサラダにかけるだけではなく、炒め油の代わりに使ったり、現地の食材や調味料と混ぜて楽しんだりすることもできます。親子でさまざまな食体験をしてみるのは、いかがでしょうか。みなさまの豊かで楽しい食生活を願っています」と話す。
(取材・文/中山恵子)