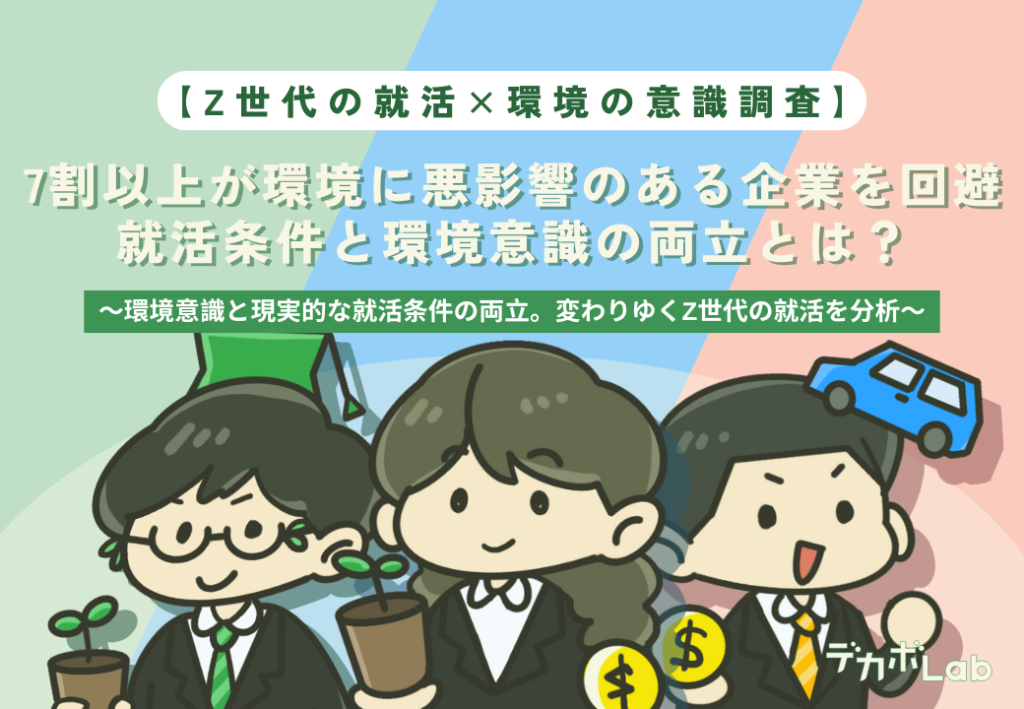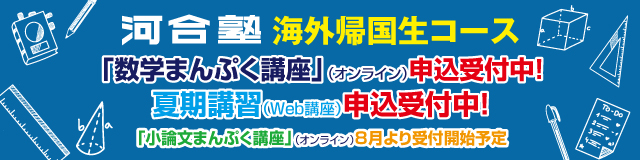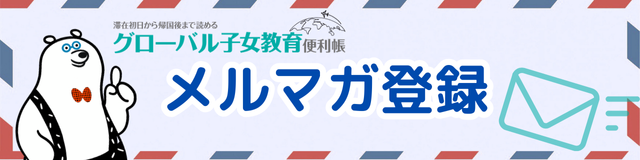川柳・短歌から垣間見える就活の実態

就活をしている学生と企業の採用担当者から募集
働き方・採用・人材育成・マネジメントなどについて調査を実施している調査機関「HR総研(HRプロ)」と、就職活動をしている学生向けのクチコミサイト「就活会議」は共催で、就活をしている学生と企業の採用担当者を対象に、就活にまつわる川柳・短歌を募集。
8月6日に入選作品を決定し、発表しました。そこには、ガクチカ(学生時代に力を入れたこと)などをどうしても盛ってしまう様子や、就活に生成AIを活用する様子など、現在の就活の実態が見てとれます。そうした実態がよくわかる入選作品を中心にチェックしてみましょう。
【2026年卒 就活川柳・短歌】
主催 :HR総研(ProFuture株式会社)、「就活会議」(就活会議株式会社)
募集期間:2025年6月17~30日
応募資格:2026年卒の「就活会議」会員
応募数 :429作品
入選作品:12作品
【2026年卒 採用川柳・短歌】
主催 :HR総研(ProFuture株式会社)、「就活会議」(就活会議株式会社)
募集期間:2025年6月18日~7月2日
応募資格:2026年卒採用を実施した企業の採用担当者
応募数 :180作品
入選作品:13作品
【就活】ガクチカを盛らない作戦や盛ってしまう違和感を詠む
最優秀賞:
「サークル長 バイトリーダー 学祭長 信憑性取り 副部長」(大阪府 バーバパパさん)
佳作:
「やったこと すべてに理由 あるように 話す私は 少し嘘つき」(東京都 無糖さん)
提出書類や面接で述べるガクチカは、どうしても少し盛りがちにはなってしまう面もあるでしょう。昨年の佳作にも「世の中に どんだけおんねん サークル長」(愛知県 まろたんさん)という作品がありました。
しかしながら今年の最優秀作のバーバパパさんは、あえて真実である「副」をアピールして信頼を勝ち取ろうという作戦をとったようです。それに対し、審査員は「肩書きのインフレが止まらない就活界で、“副部長”という絶妙なポジショニングが光る一句です。(中略)“正直”と“戦略”のはざまで揺れる就活生の等身大が見事に表現されていました」と評価しています。
理由や成果を求められる就活の中で、学生は自分の学生時代の活動にはすべて意図があり、それに応じて成長したストーリーを語るようになってしまうようです。佳作の無糖さんは、それに違和感を感じて一句詠みました。人間の活動には本来、特別な理由もなくなんとなくやっていることのほうが多いものですよね。
【就活】AIを活用しつつも、自分独自の努力を見てほしい気持ちも
最優秀作:
「手書き散る AIの筆に 風光る」(千葉県 たなかさん)
優秀作:
「AIより 人に見てほし この熱意」(新潟県 すんださん)
佳作:
「就活で・仲良くなった・GPT」(兵庫県 まかろにさん)
年々進む生成AIの進歩、就活に活用する学生も年々増加していくことでしょう。昨年はAIを詠んだ就活川柳の入賞はありませんでしたが、今年は一気にAIがらみの入賞作品が増えたそうです。
最優秀作のたなかさんは、手書きのエントリーシートとAI作成のものを、異なる企業に提出。結果、苦労した手書きのエントリーシートが落ち、AIが10分で書いたものが通過、という経験をしたよう。「風光る」AIの筆に喜ぶ気持ちもあるようですが、力を込めた手書きのほうが散ってしまった切なさがにじみます。
書く方もAIを利用する一方、見る方(企業側)も1次書類などはAIで選別するなどしています。AIを用いず魂を込めて書類を作成した、すんださんの「人に見てほしい」という気持ちはよくわかります。
まかろにさんは、生成AIのひとつであるChatGPTを相手にエントリーシートの添削や面接の練習を繰り返すうち、まるで友達のような存在になったようです。今どきの“新たな友情の形”を詠み込みました。
【就活】現代就活の一手法、「逆オファー」にもAIの影
佳作:
「落ちたのに なぜか推される 逆オファー」(埼玉県 浦和人さん)
選考で落とされたにもかかわらず、就職支援サイトを通してその企業からスカウト通知が来る、という不可思議な事態を詠んだもの。スカウトメールを送る際には、サイト側では個人を特定することなく、性別や大学名、居住地や志望動機、大学での活動などから、やはりAIを用いて選別して送っています。作品自体はAIを詠みこんではいませんが、その内情を紐解くと、やはりAIが絡んでいて、就活における生成AIの影響をつくづく感じます。
【採用】今年話題の初任給アップを詠み込む
最優秀賞:
「基本給 低いと言われて ベア検討 社内の声より 学生の声」(大阪府 ポテトさん)
優秀作:
「積み上げた 俺の処遇を 一瞬で またぎ越えてく 爆上げ初任給」(東京都 がんも3号さん)
就活川柳に続いて、企業の採用担当者が詠んだ採用川柳をみてみましょう。こちらに見てとれたのは、やはり今年日本で大いに話題となった初任給アップです。
最優秀賞のポテトさんが詠んだのは、「基本給が低い」という応募者の一言が、長年働いてきた社員の訴えをようやく浮かび上がらせるという構図。売り手市場ならではの、皮肉な実情を描いています。
初任給アップに応じ、ベア(ベースアップ)されるのなら、まだいいほうです。給料自体に実際に逆転現象が起きたかどうかは分かりませんが、優秀作のがんも3号さんは処遇全般を考えたときに、「俺の積み上げた処遇が一瞬で抜かれた!」と感じ、その悲哀をユーモアたっぷりに詠んでいます。
【採用】AI作成の書類は問題もあるが、企業側も使っている!
優秀作:
「語るほど 履歴書と違う その理由(わけ)はAIですと 君は言わずに」(東京都 ねぎさん)
佳作:
「AIで 作文作る 学生と 褒める返信 作る人事よ」(神奈川県 終わらない就職され活動で祈り続ける人さん)
昨年もAIがらみの入選作品があった採用川柳、今年も上記のように詠まれました。履歴書やエントリーシートの作成にAIを用いる学生は多々いることでしょう。就活川柳にも「GPTと仲良くなった」と詠まれたように、AIを相手に面接練習を重ねたりもするのでしょうが、やはり面接で話せば話すほどボロが出て、AIが作成した書類とは食い違ってくるようです。ねぎさんの作品には、AIに“作り上げてもらう”危うさが浮き彫りになっています。
一方、終わらない就職され活動で祈り続ける人さんの作品は、就活生のAI使用を批判するものではありません。お勤めの企業がIT関連ということもあり、企業側も応募者への返信に際し、AIを活用しているのです。この作品に対し、審査員は「技術愛あふれるユーモアが光る一句は、AI活用の最先端を示唆しているようです」と評価しています。比較的ITに弱い筆者は就活におけるAI活用を皮肉を込めて詠み込んだ川柳によりシンパシーを感じてしまいますが、技術の進歩ということを考えると、最先端のものを活用していくことはやはり必要ですね。
読みとれた世相ごとにピックアップして紹介してきたため、入選作品全点は紹介しておりません。全作品は「2026年卒 就活川柳・短歌/採用川柳・短歌」オフィシャルページをご参照ください。
(取材・文/大友康子)