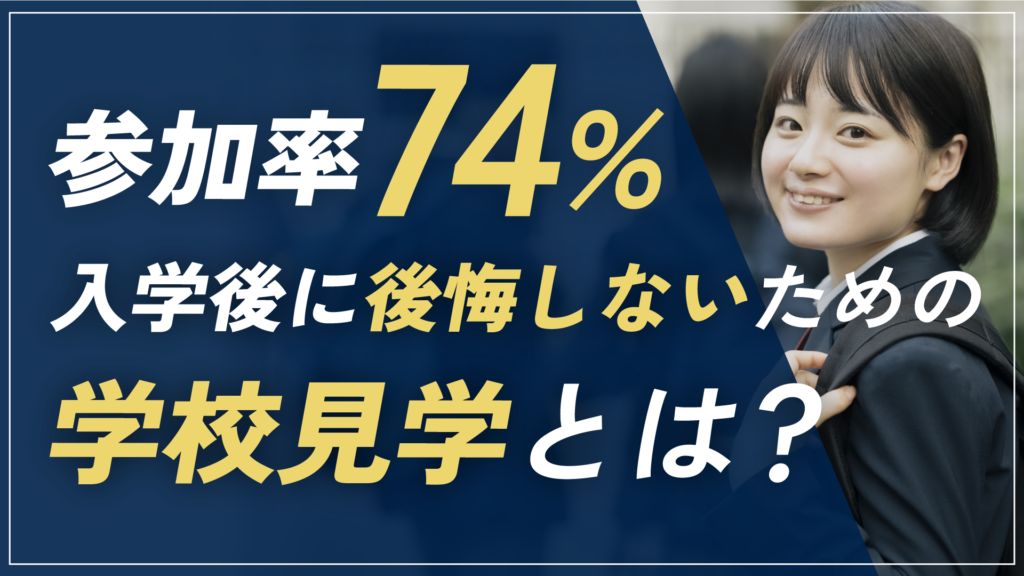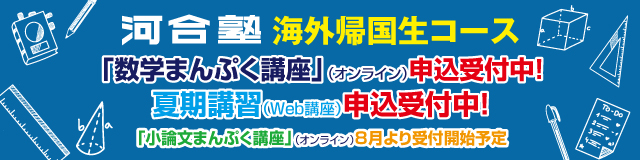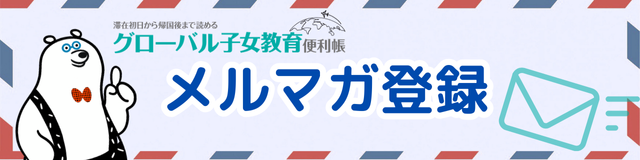【第3回】専門家に聞いた!後悔しない中学校選びとは?

中学校選びでの後悔の声には、校風や授業との相性の不一致が目立ちます。そうしたことをどう避けるか、どう乗り越えるか。中学受験カウンセラーの安浪京子氏を含む専門家にお話を伺いました。
「校則の厳しい学校を選んだが、我が子には合わず窮屈そうにしている ──」
【対応策】学校の変更も視野に入れながら動いてみる
「海外生活で『のびのびとした性格』を得て、日本で『ルールを守りながら集団行動できる力』を得たら、2つの強みが持てるようになるねと本人に伝えてみてください」(中里氏)。学校への相談も大事。「どこが窮屈なのか、具体的に把握してから相談を。家庭で努力・改善できることも伝えると、双方で落としどころを探りやすくなります。それでもうまくいかない場合は、学校を変えることも視野にいれましょう」(安浪氏)。
【予防策】先輩に感じたことを聞いて、学校の検討を
「日本の学校は丁寧で、基本的に管理体制が強め。中高一貫校で自由な校風と謳っていても『中学は管理が厳しく、自由なのは高校になってから』という学校も。また、『校則が多い』『宿題や補習が大変』など“厳しい”の種類も様々です。現実を知るには在校生に聞くのが一番。オープンスクールや文化祭などで思い切って高校生に話を聞きましょう。中学を経てきている人が多く、俯瞰して感想を話してくれるはずです」(安浪氏)。
「ネームバリューを重視して決めたが、校風やノリが正確に合わなかった ──」
【対応策】まず魅力的なところに焦点を当ててみる
「いいな、魅力的だな、と思えるところを探し、そこに焦点を当てると案外景色も違って見えるかもしれません。高校や大学への進学時、ネームバリューが課題になるケースがあることも覚えておきましょう」(中里氏)。「どうしても『違う』と思うなら学校を変えることも視野に入れ、お子さんにとって居心地のいい環境探しを。ただ中学と高校では雰囲気が異なることもあるため、中高一貫校の場合は高校まで待つ選択も」(安浪氏)。
【予防策】行き詰まらないよう、情報収集は念入りに
「ネームバリューを重視して学校選びをすると、子どもの性格や適応スピードに合わない校風だった場合、行き詰まる可能性がある。まずはこれを心に留めて学校選びを」(中里氏)。安浪氏は「知名度や偏差値で学校を選ぶ時代ではもうない」と言う。「時代も学校も変化しています。固定概念を捨て、限られた情報で選択するのをやめ、負担でもやはり学校に足を運びましょう。保護者の雰囲気も要チェックです」(安浪氏)。
「チャレンジ校を受けさせギリギリ合格できた。だが入学後の成績はほぼ最下位 ──」
【対応策】得意とする教科を伸ばせるよう応援する
「合格につながった教科の学力を評価してください。『この教科は誰にも負けない』という本人の気持ちや自尊感情が高まれば、相乗効果で他教科の学力もついてくるはず」(中里氏)。大学を目標とするなら、総合選抜型や学校推薦型選抜で合格要件を満たすような取り組みを模索するのも手でしょう。この2つの選抜方法では、評定平均値の高さを重視しない大学や募集要項に入れない大学も少なくありません」(安浪氏)
【予防策】国語・理科・社会を本人が入学前に学ぶ
「一般入試を経た生徒の多くは国算理社の4科を勉強して入学しており、数学に変わる算数以外は、授業が中学受験の延長でスタートします。ですから帰国生枠や英語入試で入学・編入学するにしても、その学校の一般入試問題は目を通して何教科レベルかを把握し、国語・理科・社会はひと通り勉強しておくほうが安心。勉強の際は、重要ポイントがコンパクトにまとまっている中学受験用の参考書や問題集がやはり便利です」(安浪氏)。
「英語の授業のレベルが合わず…。英語が公用語だった海外の学校を恋しがっている ──」
【対応策】校外で切磋琢磨できる仲間を作る
日本には、英語上級者のレベルや要望に合わせた授業を用意できる一条校は限られているという。「すなわち、同じように悩む帰国生は一定数いるということです。そうした仲間と切磋琢磨したい場合は、帰国生向けの外国語保持教室や英語塾などに通う検討を。逆に、英語の授業のレベルが高すぎるという場合は、なるべく早く学校の先生に相談してください。帰国生だからといってためらう必要はありません」(中山氏)。
【予防策】学校見学や動画で英語の授業を確認する
「学校のパンフレットだけではわかりにくいため、学校見学時に直接、英語の授業を見せてもらうのが一番です。学校の公式WEBやオンライン説明会などで観られることもある授業動画もとても参考になります。海外の学校のように討論や発表の機会が多いかも、しっかり確認を。また、先に帰国された知人の口コミも参考になります。知人であれば、お子さんの英語力をふまえたうえでアドバイスをしてくれるでしょう」(中山氏)。
「家から遠くて通学時間が長くかかるのが、思ってた以上に負担で…──」
【対応策】学校生活を楽しめるようにサポートする
「引っ越しが1つの手段になりますが、保護者の仕事やきょうだいの通学の関係で難しい場合が多いでしょう。中学生となると部活動などでの体力消耗も激しくなるもの。とはいえ、学校が楽しいと思えるなら通い続けます。難しいのが学校を楽しいと思えない場合。負担になって通学は、不登校の引き金になることもあります。お子さんが学校を楽しめるよう、保護者にできるサポートはするようにしましょう」(安浪氏)。
【予防策】経路や路線の特徴も事前に把握する
「通学時間が長くても、ずっと座っていられる場合は、乗車中に体力を温存できます。逆に通学時間が短くても、「ラッシュがひどい」「痴漢に注意する必要がある」といった場合は体力と心の疲弊を免れられません。また、塾や大学入試のための予備校に通う場合は、自宅、学校、塾・予備校の動線も重要。惚れ込んだ中学校に合格した場合、学校の近くに住居を構える家庭も少なくありません」(安浪氏)。
「取材・文/本誌編集部・庭野真美 イラスト/いそのけい」
お話を伺った方

公益財団法人 海外子女教育振興財団 中山順一(なかやま じゅんいち)氏
国際基督教大学高等学校に創立2年目から勤務。担当教科は理科(化学)。教頭として帰国生入試の書類審査などにも数多く関わる。現在は上記財団にて、教育アドバイザーを務める。(掲載当時)

臨床心理士、公認心理師 中里文子(なかざと あやこ)氏
児童相談所等で親子関係の心理支援に携わる。現在は児童精神科クリニックを中心とした社団法人METKIDSでスーパーバイザーとして活動。企業内カウンセラーとして従業員支援も行う。

中学受験専門カウンセラー 安浪京子(やすなみ きょうこ)氏
算数教育家、株式会社アートオブエデュケーション代表取締役。大手進学塾にて算数講師を担当、プロ家庭教師歴20年以上。中学受験や算数に関する著書、連載、コラムなど多数。