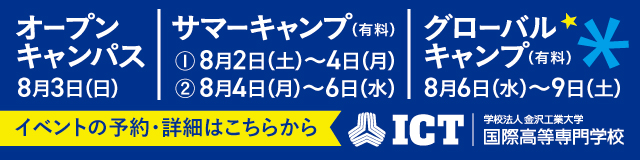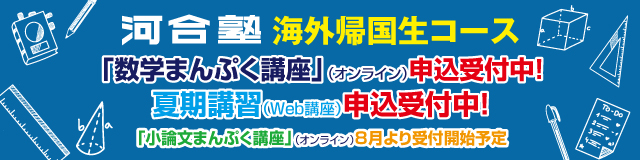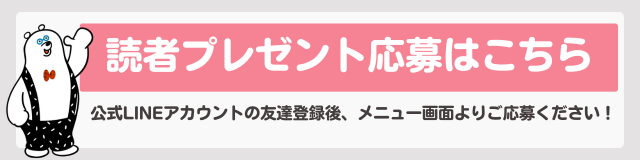専門家に聞く!小学校選びの最新トレンドとは?

小学校選びで重視されるのは知名度より教育内容や環境
昨今のニュースでは首都圏の中学受験率の高さがよく取り上げられているが、小学校受験率もコロナ渦を経てグッと上がったという。
「首都圏1都4県(東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城)の私立72校を対象に調査したところ、2023年度の志願者数は前年度比407人増の2万1691人でした。2019年度の2万1653人からは24%増えています。」(野倉氏)。
この背景には「英語教育に力を入れている学校がいい」「公立の教員不足が問題になっているため教育の質を担保しやすい私立を選びたい」「附属小に通わせて中学受験を回避したい」「共働きなのでアフタースクールの内容の充実が条件」というように、希望する教育内容や、教育環境を追い詰める様々な保護者の思いがあるという。「家庭ごとに多岐に渡る希望があり、それを中心にして小学校選びをする傾向が見られます。従来のように多くが知名度や偏差値を優先して選ぶ時代ではなくなってきたと肌で感じますね」(野倉氏)。
本誌の読者の方々からは「帰国後は英語教育が気になる」という声も多く届く。近年の英語教育での変化として挙げられるのは、日本でも国際バカロエア(IB)の初等教育課程プログラム(PYP)の認定校が増えていることだろう。PYPの認定校は2024年の時点で67校、候補校は48校。2014年の時点では認定校は16校だったため、10年で4倍以上増えたことになる。その多くは私立だが、2021年には公立初のPYP認定校も誕生している(高知県の香美市立大宮小学校)。また、IBと肩を並べる存在とされるイギリス発の国際的な教育プログラム、ケンブリッジを展開するケンブリッジ国際認定校は、インターナショナルスクールで徐々に増加中。2023年にはインターではない一条校で初のケンブリッジ国際認定校も誕生している(東京都の昭和女子大学附属昭和小学校)。「国がグローバル人材の育成を推進していることが、よくうかがえます。」(野倉氏)。
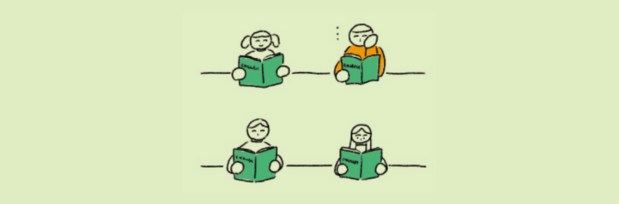
この段階での算数教育が、後の学校選びでのアドバンテージに
このほかに注目すべきはSTEAM教育を強化する小学校が増えている点だという。STEAMとは科学(science)、技術(Technolongy)、工学(Engineering)、芸術・リベラルアーツ(Art)、数字(Mathematics)の略。それらを教育横断的に学んで理数に強いイノベーターを育てようというのがSTEAM教育だ。文部科学省は、AI(Artificial Intelligence)やIoT(Internet of Things)が普及して激しく変化する時代で、活躍できる人材を育てるために、この教育を推進している。「例えば、2021年度の入試では早稲田大学政治経済学部の一般選抜で新たに数学の項目が必須となりました。『経済学や政治学では数字を使った研究が必要』という認識からとされています。もちろんこの例に限りませんが、小学生のうちから教科横断的に学ぶことや算数に強くなっておくことは、中学、高校、大学と学校を選んでいくうえでも大きなアドバンテージになりえるということでしょう」(野倉氏)。
お話を伺った方

小中高の受験情報を発信 野倉学(のくら まなぶ)氏
リクルートにて大学の募集広報戦略を担当後、株式会社バレクセルを設立。“一人ひとりにあった学校選びを”をテーマに小学校受験の「お受験じょうほう」と「中学・高校受験スタディ」を運営。